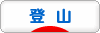GWの山行も無事に終え、その翌週末に向かった先は白砂山。
長野、新潟、群馬の3県の境にそびえる標高2139mの山で、日本二百名山にも選定されています。
知名度はそれほど高くはないかもしれないですが、白砂山は前から行きたかった山の1つで、何と言っても自分の大好きな”稜線“が見どころ。緊張を強いられたGW山行後のリフレッシュハイキングとしてはちょうど良かったです。
初夏の時期であれば麓から山頂に至るまで色んな花が咲いて、花と稜線が存分に楽しめる山。今回は時期が5月初旬だったので、花の時期には少し早かったですが、それでも足元には小さな花が咲き、夏の到来を予感させました。
何よりこの時期の目玉は、残雪と新緑が織り成す白と緑の稜線。この雪が残った山の稜線が、また大好きなんです。
期待通りの稜線、そして想定外の絶景に巡り合えた麓に広がるエメラルドグリーンの野反湖。
また1つ自分好みの山に出会えた旅でした。
白砂山、残雪の稜線を歩く―――
槍ヶ岳と北穂高岳の記録。結構な方に読んで頂いたようでありがとうございますm(__)m
去年のGWの北アルプス表銀座縦走に続いて、今年のGWの山旅も相当厳しかったけど、思い出として色濃く残るもんだったなと。
2日連続で標高3000m超の山を登ったので、翌週くらいは休んでもいいかという思いもあったんだけど、GW後半がゆっくり休めたので、すっきり疲れも消えて迎えた週末。再び山モードに入っておりました。
本当なら土日で行くつもりが、この週は土曜の天気が大荒れ予報だったので、急遽日帰りに変更。冒頭でも話した通り、稜線フェチとして前々から気になっていた白砂山をリクエストしたところ、お仲間さん達が快諾してくれたので決行となりました。
今回は前回までとは打って変わって、緊張感なしのまったり登山。
行程としては8時間程度の軽いハイクですが、個人的には大好きな山行ジャンルだったので期待せずにはいられなかった。
山はもとより、登山口に広がる野反湖に深い可能性と魅力を感じた山旅でした。
~~ 2015年5月10日 白砂山・八間山 ~~
今回も前夜発。白砂山自体の行程はそれほど長くはないんだけど、登山口までのアクセスがかなり遠い…。
高速道路を下りてからの下道がやたら長く、渋川伊香保ICから80km弱あります。
道は登山口までしっかりと舗装されているのが幸いだけど、運転手のくろちゃんには頭が上がりません。。
登山口はいくつかあるけど、今回は野反湖ダム手前の駐車場から登ることに。ここが白砂山山頂まで一番近い登山口だから、最も登られてるスタート地点だと思います。
駐車場もかなり広くて、50台は楽に停められるスペース。登山者の受け入れ態勢は万全!
ただ、寂しいことに日曜にもかかわらずこの日はわずか5台ほど。時期が少し早かったのもあるかもしれないけど、色々下調べをしても、この駐車場が混雑するような記録は全くなかったので、山自体の知名度がまだあまり高くないのかもしれない。
この駐車場には夜間でも使える休憩所とトイレがあります。(右の建物)
さらに自販機や靴の洗い場も完備されていて、登山者にはこれ以上ないくらい充実したインフラ。昼間は左の建物が売店になるらしいんだけど、早朝なのでまだ営業はしてませんでした。
休憩所の中はこんな感じ。この日は朝から強風が吹き荒れていて、外が物凄い寒かった…。
なので、この休憩所が本当にありがたくて、ここで朝ごはん食べたり着替えたりして出発の準備を整えました。
登山口前には、こんな立派な地図もあります。今回利用する登山口は野反湖の北側の現在地となっているところ。他の記録を見ると、南の富士見峠から登っている人もチラホラいました。
最短ルートは今いる登山口なんだけど、南の富士見峠は時期がもう少し遅ければシラネアオイやコマクサの群生地が登山口付近にあるので、時期次第ではそちらをアタック拠点にするのが良いかもしれません。
今回は堂岩山~白砂山~八間山と登る周回コース。白砂山から八間山に素晴らしい稜線が広がっているから、どのルートで登るにしろ、この2つの山はぜひ周回してほしい。
登山口正面に見えたお山。
こちらは今回は登らない西側の高沢山と三壁山。山頂が見えているので簡単に登れそうだけど、上の方は樹が少なくて見るからに展望が良さそう。
稜線も穏やかに見えたし、時間があれば登ってみたかった山です。
こちらが白砂山登山口。だいぶ車で上の方まで登ってこれたので、標高1530m地点からのスタート。
標高で言えば上高地に匹敵。ただ風が強い分、前週の上高地に比べると格段に寒かったです。
7時前に登山開始。まだ所々固まった雪が残ってたけど、アイゼンつけるほどでなかった。
残雪の状況以上に気になっていたのが、この日の天気。強風は事前の予報で知っていたので別に問題はなかったけど、3つの県境に位置しているので、どのエリアの天候を参考にしてよいのかが微妙だった…。
近隣にある名山としては、長野側に草津白根山、新潟側に苗場山、群馬側に谷川岳という位置関係。その中心にある白砂山。谷川岳方面がこの日は終始ガスの予報だったけど、長野側の天気が快晴と出ていたので、それに賭けての白砂山になったというのもあり…。言いだしっぺでガスられたらどうしようもなかったけど、強風が雲の流れを群馬側に押しやって、上空は徐々に青空が広がってくれてました。
天気が良いと、登りはじめて早々に1つの絶景にありつくことができて……
それがこちらの野反湖。この後も何度も見ることになるけど、水の色がとにかく綺麗。高い標高に位置している分、周りの山との高低差が少ないので、周りの雰囲気にしっかり溶け込んでいるのもいい。空も近く感じる。
陽が当たらないこの時間はオーシャンブルー。これが日中になるとエメラルドグリーンに変化して、さらに綺麗な景色を見せてくれる。
この時点では、山頂方面がまだ雲の中だったけど、風で雲がみるみる流れていくので、何となく大丈夫そうな予感がした。
厄介に感じていた強風も、頼もしく思えてくるから不思議。ガスった稜線なんて歩きたくないから、頼むから雲を吹っ飛ばしてくれ!
登山道としては少しだけ登って、いったん沢まで下る。薄らトレースがあったので迷わなかったけど、残雪時にそこまで入山する人がいないようなので、状況次第ではここら辺はやや迷うかも。
このハンノキ沢を渡るのが正解。壊れかけた橋とこの標識が目印です。
白砂山まで5.7kmってなっているけど、それがすごく近く感じるのは、たぶん前週の槍ヶ岳のせいだな(笑)
ここからしばらくは樹林帯の登りが続くけど、堂岩山まで登ってしまえば後はお待ちかねの稜線が始まるので、頑張る部分としては3.6kmだけ。
陽が当たらない部分はまだかなり雪が残っていて、探りながら登っていく。
GW前なら確実にルートファイティングが必要なので、迷うのが心配ならヤマレコとか見てある程度先客を待った方が良いかもしれません。
登山道わきに咲いていたのがショウジョウバカマ。群生とはいかないまでも、足元を見るとチラホラ咲いていて、目の保養になりました。
登山初期の頃なんて足元に目を向けたことなんてほとんどなかったから、こういう花は見逃していたと思う。そう考えると、何と勿体ないことをしていたんだろう……
朝はかなり寒かったけど、樹林帯に入ると風も収まって、暑くなってくる。
自分の理想形としては、なるべく脱ぎ着はせずにスタートの服装のまま山頂まで行くことなんだけど、風が強いとやっぱり難しいな…。暑がりな体質なんで、できることなら半袖で行動したい派なのです。一方で重度の寒がりでもあるので、スタート時は着込んでしまうというね…(^^;
途中にあった廃屋。白砂山の記事を見ていると、みんなこれを載せていたので、自分も流れに合わせて載せておきます。
何の用途で建てられたかは不明。
緑の小さな息吹。
5月ともなれば標高2000mの山でも新緑を迎えつつある季節。いよいよ雪も終わり、夏山シーズンの到来を予感させます。
登っていると何度か展望開けた尾根に出る。
雪が積もっていてくれると、その分が足場となって視界も広がる。
眼下に見えるのが先ほどの野反湖。こうして眺めると、湖自体が山の上に広がっているのがよくわかる。
湖の綺麗さはもとより、周りを取り囲む山の雰囲気がまた良くて、トレッキングコースやキャンプ場も充実している。野反湖メインで遊ぶのも楽しいかもしれない。
尾根にはハート型の残雪も発見。男子登山でも、こういうのを見るとキャッキャするんだぜ!
雪と緑を同時に楽しめるのが、この時期の標高2000m級の山の魅力。
途中の水場への分岐。水場の状況は確認してないのでわからないけど、ルート上ではここが唯一の水場。
今は寒いとはいえ、標高2000mを少し超えるだけの山なので夏場はかなり暑いと思う。水は多めに持って行ったほうがいいです。
標高1800mを越えたあたりはほとんど雪。
たまにルートを外しつつ、トレースや赤テープ探したりGPS確認したりで登っていく。
樹林帯の合間から見える野反湖。
あまりの綺麗さに、どうしても目が行ってしまう。
堂岩山までのラストの登り。多少の登り返しはあるけど、基本的に登山口からここまで急登と感じられるようなところはなかったです。
9時10分、堂岩山に到着。これから向かう白砂山も八間山も雪が完全に融けていたけど、この山頂だけがまだかなり積雪ありました。
標識だけこんな感じでくり抜かれてた。
残雪分だけ標高上積み。展望もその分開けて見える。
こちらが白砂山。まだ距離は少しあるけど、これから歩く何とも楽しそうな稜線が見えてしまったので、テンション上がらずにはいられなかったな!
心配していた雲も、白砂山の背後までどいてくれました。
雪が積もっていてくれたので西側の展望も良く見えた。
手前が相変わらず綺麗な青の輝きを見せる野反湖。その向こうに見える高い山が草津白根山。
野反湖の綺麗さは本当に想定外で、周りの名山さえ霞ませる。山旅のオプションとしては贅沢すぎる付加価値でした。
心配だった雲は全部群馬県側に流れて、そちらには雲海が広がってました。
谷川方面の山に登っている人には申し訳ないと思う反面、稜線を境にここまで天気が変わるもんなんだな~と山の天気の変化に一人感嘆としておりました。
ここからいよいよお目当ての稜線ハイク開始!
この稜線を歩きたくて遥々やってきたわけだから、じっくり堪能させてもらう。
稜線に差し掛かってすぐに堂岩分岐点。まずは標識通りに白砂山まで登って、帰りは八間山経由で帰る。
八間山に至る稜線も素晴らしいのでそれは後ほど。
稜線上に咲いていたのはミネザクラ。これから満開を迎えようかって頃合いでした。
雪が残る稜線。この残雪が良いアクセントになって、緑の稜線がひときわ綺麗に見える。
稜線の風景としては、この適度に雪が残った状態が一番好きかもしれない。
山の斜面にもちらほら残雪が残る。見ての通り、山の斜面に背の高い樹木がないので、稜線上の開放感が素晴らしい。
標高2000m程度でこの展望が得られるのは、谷川岳に通じるものがある。
稜線から良く見えたのが、南側に聳える榛名山。普段はあまり意識して見ない榛名山だけど、この白砂山からだと多数の峰を有する複雑な山容が一望できる。
一見した時に、八ヶ岳と見間違えたのはここだけの話(笑)
稜線上は基本的に道が整備されているけど、一部藪漕ぎっぽいところもあり。
この日は乾いてたから良かったけど、雨上がりはかなり濡れるかもしれません。そういう場合、パーティーで登るなら最後尾からついて行けばあまり濡れないけど、仲間のひんしゅくを買う可能性大なのでご注意を!(大源太山での経験談)
稜線と並行して北側に見えた山が八十三山。地図で見た限りでは一般ルートはなかったけど、あちらの稜線も気持ちよさそう。
八十三山の名前の由来が全く分からなかったので、誰かわかる方いたら教えてください。何が八十三なのかと…
石板のように砕けた雪のブロック。この砕け散り様、なんでかドラゴンボールを思い出してしまった。
この日、稜線上で出会った登山客は5人程度。静かな稜線がまた良かった。
稜線途中の猟師の頭。地図には載っていなかったポイント。
行きはただの通過点だけど、帰りに見ると1つのピークに見えます。山頂まで残り1.3km。
ここから山頂までは、ご覧のような登り返し。
岩に張り付く苔がまた綺麗。
稜線でも細かく見れば見どころも豊富。
朝から強かった風は、この稜線に入ってもあまり弱くなることがなく、たまに強風で身体持っていかれそうになったりもしました。
日中になって気温が上がってきたので、歩いている分にはちょうど良かったか。
山頂手前の金沢レリーフを通過。
最後の登り。急登と言えるところは、登りではここくらいでした。
この登りも数分なので、登りのルートとしてはかなり楽なもん。序盤の残雪による道迷い以外は危険箇所がないので、体力的にはそこまで求められない山です。
日差しが当たるけど、風が強くて涼しいので登っているとちょうどいいくらい。前週の槍・北穂を登っていた時の方が全然暑かった。
ニセピークが少しあり。下から見えていたのは山頂ではなく、ピークは少し奥まったところでした。
10時20分、山頂到着。白砂山の山頂は大して広くはないけど、誰もいなかったので堂々と羽を伸ばせた。
山頂からの展望。下には歩いてきた稜線、左奥に見えるのが草津白根山、右奥に見える真っ白な山が志賀高原の岩菅山とか。
残雪が良いアクセントとなって素晴らしい山の風景が広がっていました。
こちらは白砂山からさらに先の稜線。ここから先は人があまり立ち入っておらず、悪路らしいので一般ルートにはなってないです。ただ、稜線伝いに歩いて行くと、白砂山と同じく二百名山に選定されている佐武流山にも行きついたりして開拓し甲斐がありそう。
白砂山は長野、群馬、新潟の3つの県にまたがる山だけど、その3県の境界線が交わるところもこの山頂ではなく、ここから少し先へ行ったところ。
そういう意味でも、この稜線をもう少し先まで歩いてみたくなる。
そういえば、グレートトラバースが今度は日本200名山一筆書きに挑戦し始めましたね。佐武流山へ行くときは、北側の正規ルートじゃなくてこの稜線を突っ切って行くんでしょうね、きっと……
高速下りてから長い下道を走ってきただけあって、街らしきものが全然見えない。決して高くはないけど周囲山だらけで、山深さを感じます。
こちらは浅間山。雪が消えると山座同定もわかりづらくなってくる。
谷川岳、苗場山方面は雲に隠れて見えませんでした。
まだ11時前だったのでお昼ご飯といえるか微妙だったけど、せっかく貸切だったので山頂でご飯休憩。
暖かければ長居したかったのだけど、風が強くてジッとしていると寒かったので、結局30分くらいで撤収しました。
歩いてきた稜線を戻る。同じ道だけど帰りのほうが八間山に至る稜線まで見えるので、改めてこの稜線の雄大さを知ることができる。
展望の良い稜線ハイクはやはり何よりも好き。稜線上のアップダウンならそこまで苦にならずに楽しめる。
こちらが来たときに通った猟師の頭。行きでは気付かなかったけど、岩場のピークでした。
5月の稜線は緑と雪の共演が見れるのがまた楽しい。
稜線の雰囲気としては上州武尊山の剣ヶ峰へ至る道に似ている。上州武尊山は夏と冬に登ったけど、どちらの時期も楽しい山でしたよ。特に冬場は谷川岳を越える面白さでした。
記念に1枚。冬は道路が封鎖されるので、 アクセス的に厳冬期に訪れることはほぼ不可能に近い山だけど、こういう穏やかな稜線とはっきりとしたピークの山容は雪の時期に登っても絶対に楽しいはず!アクセスさえ良ければもっと人気が出る山だと思いました。
目の前の山が堂岩山。左奥に見える少し低い山が八間山。
稜線ははるか先まで続く。
堂岩分岐点まで戻ってきて、そのまま八間山方面へ。
この先も展望豊かな稜線が続く、楽しい時間。
稜線を伝って右奥に見えるのが八間山。その手前に1ヶ所だけ大きな登り返しがあります。
基本的にこちらの稜線も緩やかで楽に歩けます。
風もこの時間帯はだいぶ弱くなってくれました。
中尾根の頭。地図上にはない標識がたくさんあって、少し親切すぎるくらい小刻みに距離を教えてくれる。
振り返って見る白砂山の稜線。雪の残り具合と稜線のアングルから見ても、ここら辺から見る白砂山が一番綺麗に見えました。
白砂山だけでも楽しめるけど、時間があるなら絶対に八間山も周るべき。
途中、一気に下る箇所あり。いったん樹林帯に入って、少し勿体ないくらい標高を下げます。
倒木のトンネルを抜けて、光の差す方へ……
そこで待っていたのが、この登り返し。雪の部分が一見すると傾斜が緩いように見えるけど、これが見た目よりも結構きつくて、ここの部分だけは男5人も無言になったな(笑)
白砂山~八間山を歩くなら、どちらから登ってもここの登り返しは避けられないので頑張るしかない。
ここまでが楽すぎてハイキング気分になってしまったので、余計に辛く感じたのかもしれない。
登り切ったところが黒渋の頭。
あとは八間山まで小さいアップダウンを繰り返していけば着きます。
稜線に敷かれた1本のトレッキングルート。これがまた好きな風景なんだな。
この手の緑豊かな稜線は、上信越特有のものだと思っている。巻機山や上州武尊山も同じで、一面ハイマツ帯や岩場のアルプスの稜線とはまた別の魅力を備えている。
八間山は標高2000mを切っているけど、それでもこれほど開放的な稜線が用意されている。
稜線フェチとして、やはり選んで間違いはなかった。
山頂手前に、ここにも廃屋。いったいどのような用途で建てられたものなんだろうか……
13時すぎ、八間山に到着。
標高は1934m。白砂山よりも200m程低いけど、山頂の広さはこちらの圧勝。そこそこの大人数でも問題ない広さだし、簡易ベンチも用意されていました。
展望もこちらの方が上かもしれない。白砂山へ至る稜線を一望できる。
こうしてみると結構距離があるように感じるけど、実際に歩くと2時間くらいで着いちゃいました。その間、ほぼ展望の良い稜線なので飽きることがない。
本当に山深い場所。これだけ周りが山だらけでも、高い山が他にないから眺望もいい。アクセスしづらい場所ではあるけど、展望に関していえば立地条件が優れているということか。
草津白根山もかなり近くに見える。過去に一度しか行ったことがないので、また観光ついでにでも登ってみたいけど、いかんせん火山だから以前よりは敬遠してしまう…。
後は下山するだけだったんだけど、今回ルートミスを犯したのがここ。
池の峠方面に下りなきゃいけないのに、野反峠方面の稜線をそのまま進んでしまいました。地図を見誤って、この先に分岐があると思ってたんだけど、良く見たら八間山から少し戻らなきゃいけなかった。
間違ってしまったけど、ここから先の道も気持ち良さそうで歩いてみたかったし、この先に時期が合えばシラネアオイとコマクサの群生地があるので、花が咲いている時期ならむしろこちらへ降りたほうがいいかもしれない。
一向に分岐点がなくて、これくらい降りたところでようやく間違いに気づいた。
ここで無駄な登り返しで体力を削る…。
それでもこちらに来ると、また足元に小さい花がたくさん咲いていたので、収穫はあり。
まぁ、あのまま下りてしまったとしても駐車場までプラス1時間遠回りになるくらいだから、そんなに影響はなかったけどね。
八間山まで戻って左の脇道へ入っていく。残雪があったので少しわかりづらかったです。
下山路に入って再び見えてきた野反湖。色はもはや南国の海だな!風で波立っているようにも見えました。
こちらのルートは残雪時期だと樹が密集してかなり迷いやすいので少し注意が必要。
多少のルートファイティングとGPS頼りに進んだ部分もあるので、心配なら遠回りでも自分たちが間違えた野反峠へのルートを行くのが安全かもしれません。
残雪が消えていれば全く問題のない道。ひたすら下りなので、迷わなければ標高を一気に下げて短時間で降りられます。
野反湖も大きく見えてきた。朝方は真っ青な色をしていたけど、陽が当たっている今は綺麗なエメラルドグリーン。
ここまで野反湖に魅了されるとは全く思ってなかった。
道迷いで多少のタイムロスはあったけど、14時半には登山口に出れました。
ここは池の峠駐車場。残雪が邪魔をしていて、この時期は3台くらいしか停められないスペースだったけど、この日は誰も利用してなかった。やはり自分たちがスタートした駐車場か、もしくは野反峠からのルートが定番のようです。
駐車場までは少しだけ道路を歩いて戻る。
野反湖が本当に綺麗すぎる!砂浜も見えるし、もはや湖という名のビーチ。
白砂山を語る上で、野反湖は絶対に外せない。
14時50分、駐車場に戻る。位置的なものもあるのか、朝と同様に山から吹き下ろす風が強くて、ここはかなり強風でした。
片づけをしていても色んなものが吹っ飛ばされたので、ささっと撤収。
そういえば、ちょうどバスが来てました。ここまでバスが通ってるのは知らなかったけど、長野原草津口駅というところから野反湖まで1日数本バスが出てるみたいです。公共交通でも来ようと思えば来れる山。
帰りがけに何度眺めたかわからない野反湖を見納め。野反峠に湖の展望台が用意されてました。
雲の位置が近くて、山の上に広がる湖というのがよくわかる。周りを取り囲む山の雰囲気がまた良くて、南国さえ思わせる。白砂山と合わせて、ここはもっと注目されるべき場所だと思いました。
下山後の温泉は、尻焼温泉という川底から湧き出る天然露天風呂が近くにあるので、良ければ寄ってみてください。無料で開放されているそうです。
他にも麓にいくつか温泉があったんだけど、どこも狭かったり露天風呂がなかったりしたので、インター近くまで行ってから入ることにしました。
利用したのは、「小野上温泉 さちのゆ」。
広くて綺麗で、410円というリーズナブルな料金設定に魅かれてここにしました。今はなかなか400円台で入れる日帰り温泉って少ないから、節約登山としてはありがたい。
登山としては8時間くらいの行程だった今回の旅。前回の13時間の山行に比べたら短かかったけど、今回も朝から日が暮れるまで遊んで帰りましたとさ。
期待していた白砂山の稜線。残雪もちょうどいい具合に残っていて、緑と白のコントラストが最高に綺麗。
歩いていても開放感抜群だったし、期待通りのハイクができました。八間山の稜線も穏やかで歩きやすかったし、山頂も広いのでここはぜひ縦走してほしい山です。
そして、忘れてはならないのが麓の野反湖ね!麓でキャンプして1日は野反湖で遊ぶのもありかもしれない。それくらい野反湖には魅力を感じました。
白砂山は花の山でもあるので、むしろこれからがシーズン。稜線上にも花がどんどん咲いて彩りが増すと思うので、ぜひ稜線好きの方、登ってみてください!稜線フェチとしては強く勧めておきます。
残雪の稜線、白砂山の旅でした―――
おしまい
【日程】
2015年5月10日 快晴
【コースタイム】
白砂山登山口(6:50) — 堂岩山(9:10) — 白砂山(10:20~10:50) — 堂岩分岐(11:40) — 八間山(13:10) — 池の峠登山口(14:30) — 白砂山登山口(14:50)