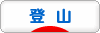新潟県と福島県にまたがる浅草岳(標高1585m)へ登ってきました。
この山に登った目的はただ1つ、ヒメサユリの大群生を見たかったから。この花はそう簡単にはお目にかかれないもので、東北エリアの一部の山にしか咲かず、絶滅危惧種にも指定されている高山植物の中でも貴重な花。
そんな珍しい花の群生を見せてくれるのが浅草岳。開花するのは梅雨に入った6月中旬から7月上旬にかけてで、南岳~鬼ヶ面山~浅草岳の稜線上にその群生を見ることができます。
ちょうど満開に差し掛かったタイミングだったので、登山道を覆うほどの見事なヒメサユリを拝むことができたのですが、実はそれ以上に素晴らしかったのが、鬼ヶ面山から浅草岳にかけての断崖絶壁の稜線!浅草岳山頂自体は木道が敷かれた穏やかな湿原風景が広がっているのですが、六十里登山ルートを歩くと浅草岳のもう1つの顔に出会うことができます。
ヒメサユリと合わせて、この断崖絶壁の稜線も強く勧めたい山行となりました。
ヒメサユリ満開の浅草岳―――
巻機山、越後駒ヶ岳、八海山……、新潟県を代表するこれらの名峰は越後山脈に属しているもので、浅草岳もその一角。
今回求めたヒメサユリが多く咲くのが、この越後山脈の山々。他だと飯豊連峰や朝日連峰くらいでしか見ることができず、ヒメサユリのほとんどが新潟の山に集中しているのが実情。東北の花の名峰とされる焼石岳とか秋田駒ヶ岳とか鳥海山とか、、、そういう山でも見ることができない、本当に限られた地域にしか咲かない高山植物。
自分の中ではかなり貴重な花として格付けされているヒメサユリ。
浅草岳は日本三百名山に選定されているものの、近隣の名峰と比べると知名度はそこまで高くはないかもしれない。標高もそんなに高くはないし、コースタイムも大して長くはなく、どのルートでも日帰りで登れてしまうコンパクトな山です。
だからこそ、登ってきた今となっては、この山を猛烈に人にお勧めしたい!
浅草岳そのものよりも、六十里登山口ルートを強く勧めたい!
ヒメサユリはもとより、山頂まで続く断崖絶壁の稜線がそこらでは早々味わえない迫力がありました。穏やかな湿原広がる浅草岳とはまるで違うもう1つの裏の顔、これこそが浅草岳の本当に魅力だと思います。
~~ 2016年6月18日 浅草岳・六十里登山口ルート ~~
浅草岳に登るルートはいくつかありますが、おそらく一番登られているのは北側のネズモチ平登山口。標高800m地点からスタートできる最短ルートで、山頂まで約3時間。最も楽に登れるお手軽ルートです。
対して今回自分たちが選んだのは南側の六十里登山口ルート。アップダウンが多く山頂まで4時間半ほどかかります。ネズモチ平ルートと比べるとロングコースですが、ヒメサユリの一番の群生が広がるのがこのルートの稜線上と聞いていたので、こっちにしてみました。
結果的には大正解だったと思います。
夜のうちに出発して、六十里登山口駐車場に到着したのが早朝5時ごろ。その時はまだ空いていたのですが、2時間ほど仮眠して起きてみたら、駐車場が満車で路駐も発生している状況でした。
この駐車場は広いし、事前情報でも空いている写真しか見てなかったので、この混雑っぷりは意外。他の方とお話したら、みんなヒメサユリ目的だろうということで……
ヒメサユリ効果、恐るべし。
この駐車場は新潟県と福島県の県境にあります。トンネルを抜ければそこは福島県。
このトンネルの先には、もう1つ田子倉只見沢登山口があって、どちらかに自転車をデポして周回ルートを組む人も結構います。こちらの駐車場にも、いくつかバイクがデポされてました。
六十里登山口はこちらの新潟県側。奥の車が2台ほど止まっているあたりに入口があります。
後々知ったのですが、この駐車場に停めている人全員が浅草岳を目指すわけではなく、途中の鬼ヶ面山までという人もかなりいたようです。
なので、車の台数に比べて稜線上で出会った人の数は少なかったです。
こちらが登山口。赤い登山ポストが目印。
7時30分すぎに登山開始。この日は午後から晴れる予報なので、あえてやや遅めにスタート。
浅草岳のコースの中では健脚向けのロングルートとされていますが、それでも往復8時間も見込んでおけば登って来れるので、この時間からでも日帰りは十分可能。
最近はソロが多かったけど、今回は久しぶりにお仲間さんとの登山。会津駒ヶ岳以来のくっしー先生、よろしく!
最初の30分ほどは登りが続きますが、そのあとはいったん平坦な道になります。1ヶ所渡渉ポイントもありましたが、特に危険個所もなし。
地図には載っていない送電線巡査路の分岐点がいくつかありましたが、標識が建てられているので迷うこともないかと思います。
40分ほど登ってマイクロ中継局がある広場に到着。何のマイクロ波を受信してるんでしょうかね……?
最初に花らしい花が見えたのは、こちらのタニウツギ。確か前回の焼石岳登山でも最初に見れたのがこの花。
登山開始を告げる花として自分の中で定着しました。
マイクロ中継局から先も比較的道は緩やかです。周りが草木で覆われてますが、地形的にはすでに稜線上にいるので、たまに展望も開けたりする。
花も徐々に多くなってきます。
いきなり出た、ギンリョウソウ!
不気味なオーラを放つ白い花。茎の透明色を見てるとゾクゾクするわ……。
足元に結構な数が咲いてました。
マイヅルソウ。こちらはなんとも可愛げのある花。
コイワカガミ。4月以降、山に登ればどこかしらで必ず見ることのできる定番の山の花。
アカモノ。白い花だけどアカモノっていうらしい。
茎が赤いからかな……
登山口から1時間半ほどで最初のピーク、南岳に到着。
この時間帯はまだガスが残ってましたが、稜線上の岩壁が早くも見えてくる。
浅草岳は湿原広がる山というイメージしかなかったので、この岩々しさが見れただけでも思わぬ収穫でテンション上がった!
帰りにはガスも取れて、素晴らしい絶景を見せてくれることになりました。
ここから本格的な稜線ハイク開始。
そして、求めていたヒメサユリのピークが早くも訪れます。
稜線の登山道を取り囲むようにいきなり咲き出したヒメサユリの群生!
景色が華やかなピンク色に染まる。
これぞ見たかったヒメサユリ。限られた山の限られた場所にしか咲かない、文字通り「高嶺の花」。
早くも出会えてご満悦でございます!
帰りに周りの景色の写真は載せるけども、稜線上からの展望も素晴らしいものがあります。
切れ落ちた崖のようになっているので、高度感も凄まじい。
ゴゼンタチバナ
この花も稜線上にたくさん咲いてました。
ウラジロヨウラク
雨上がりのしっとりと濡れた花が、瑞々しくてまた綺麗。
細い稜線を進んで行く。この時にはごく普通の稜線に感じたけども、実はすごいところを歩いているっていうことに、後々気づかされます。
噂通りヒメサユリの群生が素晴らしかった。開花のタイミングもバッチリで本当に来てよかったです。
これほどたくさんのヒメサユリが咲く花ってたぶん浅草岳以外にないんじゃなかろうか……
この後もヒメサユリは見れますが、南岳から先の稜線が一番の群生地でした。
9時30分、鬼ヶ面山に到着。狭い山頂にたくさんの人が休憩してました。話を聞いたところこの山で引き返す人も多いようです。
ヒメサユリの群生の大半はこの鬼ヶ面山~南岳の間の区間に集中しているので、確かにヒメサユリ目的ならこの山まで登れば十分に満足できると思います。
自分たちは先へ。
この先は花よりも稜線の大岩壁に目を奪われます。
徐々に取れていくガス、そこから姿を現す大岩壁の迫力がまた凄まじい!
ヒメサユリと並んで六十里登山ルートのもう1つの魅力がこの岩稜帯。
良く見ると、断崖絶壁のすごい所を先行隊が歩いてる。
稜線フリークとしては唸るしかないこの稜線!前評判にこの岩稜のことは聞いてなかったので、かなりのインパクトがありましたよ。
断崖絶壁の前にまずは北岳へ。目の前の山が北岳ですが、ピークが不明瞭で標識も特にありませんでした。
北岳から浅草岳へと続くやせ尾根。ここから、先ほど見た絶壁の稜線へと入っていきます。
まずはガクッと標高を下げるのですが、ピストンの場合、この北岳への登り返しがかなりの急登で辛い箇所になるので覚悟しておいてください。
ウスユキソウ
この花を見ると、昨年の7月に登った早池峰山を思い出す。
目の前に次々と現れる岩壁がとにかく大迫力!
目にする景色は凄まじい世界ですが、実際は断崖絶壁を歩いている感覚はほとんどなくて、登山道自体はしっかりと歩きやすいです。危険個所も大してないので、誰にでも歩けます。
ベニサラサドウダン
集中的に咲いているところがあって、緑の稜線を紅く染めてました。
北岳と浅草岳のちょうど中間あたりにムジナ沢カッチというポイントがありました。
標識は草にほぼ隠れて、自分でも良く見つけたなぁと思うところ。普通に歩いていれば通り過ぎるところだと思います。
標識のすぐ近くに蝶がとまっていたのでパシャリ。蝶の種類なんて全然わからないけど、軽く調べたらヒオドシチョウという蝶に似てたのでたぶんそれかな。
花を観察していて思ったのが、葉っぱも1つ1つ特徴的な形してて見ていて結構面白かったです。
だいぶ霧も晴れてきて、浅草岳本峰も目の前に。
アップダウンが多くてなかなか歩き応えのある稜線。全体的に道が狭くて休むポイントも少ないので、大人数で列を成して歩くには不向きなコースかもしれません。
ストイックに浅草岳の魅力に迫りたい方向けのコース。それが六十里登山口ルート!
岩の門。崖になっているのではるか下の沢まで見通すことができます。
ヤマツツジも咲いていた。
稜線上は花も豊富です。
歩いている分には岩壁の淵を歩いている感じがまるでしない不思議。道幅は終始これくらいなので参考までに。
見て分かると思いますが、登山道自体には岩場はほとんどなくて土と緑の道続きます。それゆえ花が豊富な分、ぬかるみが激しい箇所もあったりする。
終盤にもヒメサユリのお花畑がありました。ヒメサユリの数は南岳の群生に比べると少ないですが、他にも色々と花が咲いていて、ここが一番「お花畑」という感じがしました。
中でも見れてうれしかったのがニッコウキスゲ。
ニッコウキスゲには少し早い時期だと思ってましたが、せっかちな早咲き君がすでに咲き始めてくれてました。花の大きさと形がヒメサユリにそっくりなので、ピンクと黄色の共演が本当に綺麗だったな~
最後がやや急登。ぬかるんでいる箇所もあって、一部神経使うところもありました。
今回歩いていて幸いというか幸運だったのが、虫が少なかったこと。事前の情報では、ヒメサユリの時期はブヨやらハエやら、やたら飛び交う虫が多いらしく、この日も虫よけネットかぶっている人や蚊取り線香持っている人がたくさんいました。
標高が低いので、まぁ仕方ないということで多少の覚悟はしてたけど、拍子抜けするほど全然気にならなかったレベル。
明け方の気温が低かったからなのだろうか……。ひどいときは立ち止まるのも億劫なほど虫がたかるそうなので、飛び交う虫がダメな方はそれなりの対策をした方が良いかもしれません。
ネズモチ平登山ルートとの合流地点手前でもヒメサユリ。なかなか見ることのできなヒメサユリも、ここら辺まで来ると見慣れたものになってくるから恐ろしい。
これほど貴重なヒメサユリがたくさん咲いているのに、なんで花の百名山に選定されていないんだろうって思ったけど、よくよく調べてみたら新・花の百名山にはしっかりと選ばれてるようですね。
実際に登って景色を見てきた身としては選ばれて当然だと思った。
11時過ぎ、ネズモチ平登山口側のルートと合流。ここまで来れば、浅草岳山頂は目と鼻の先です。
写真右奥に見えているピークがそれ。
山頂手前にかなり大きな雪渓が残ってました。斜面は割と急ですが、登山者が多くてステップがしっかりしていたので軽アイゼンは特に必要なかったです。
雪渓登ってまず目に飛び込んできたのが、まさかのパラグライダー(笑)
こんなところから飛び立つとは……。浅草岳がパラグライダーで有名なのかは知らないけど、最短ルートのネズモチ平登山口からでも3時間はかかるので、良くここまで登ってきたもんですね。
当然ながら注目の的となってました。
山頂まで続く穏やかな木道。先ほどまでの断崖絶壁の岩稜とは打って変わって穏やかな登山道。
…というか、浅草岳で本来イメージしていたのはむしろこっちの世界。ネズモチ平登山口から登る人にとっては、おそらくこの山頂付近の木道が気持ち良くてインパクトでかいんでしょうね。事前の情報で良く見たのはこの山頂に広がる木道でした。
木道散策を楽しんでいる間に、パラグライダーテイクオフ!
この後、山頂から下山するまで空中散歩を楽しんでいたので、パラグライダーって一度飛び立つと長時間遊んでいられるんですね。風も穏やかでなんとも気持ちよさそうでした。
11時30分、浅草岳山頂に到着。休憩込みで4時間程度の登りでした。
時間で言ったらそれほどの長距離ではないけども、帰りも同じ道(アップダウンある稜線)を歩くことになるので、余裕を持った登頂でちょうどいいくらい。
山頂はそこまで広くはないですが、視界が開けていて展望良好!
予報通り、青空も広がってきてくれました。
目の前に見えるのがこの田子倉湖。十字型になっている面白い形の湖です。ここで初めて田子倉湖の写真を載せたけど、六十里登山口から登れば、序盤からずっとこの湖は見えてます(笑)
湖フリークなるものがいるのかわからないけども、この十字型をしっかり目に収めるなら山に登るしかない。温泉好きが秘湯を求めて山登りを強いられるのと同じ。
そういう意味では山登りを難なくこなせるっていうのは、かなりのアドバンテージだと思うんだな。
ピークは踏んだけども、この先にどうしても見ておきたかった場所があるので、もう少し先まで行ってみることに。
その場所がこちら。山頂直下に広がる湿原、天狗ノ庭。台地のように開けた場所に木道が敷かれてました。
あそこまで降りてみようかとも思ったけども、向こうから歩いてきた人に花はほとんど咲いてなかったと聞いたので、眺めるだけに留めました。
今回歩いた六十里登山ルートが少し異質なだけで、本来の浅草岳の登山ルートはあのような湿原広がる木道が醍醐味。浅草岳が尾瀬に近い雰囲気というのは決して間違ってはいないと思います。
山頂は混んでいたので、少し下った木道の所で休憩することに。
写真奥に見えてる山が、登ってくる途中にあった北岳。山頂にいる人の大半はネズモチ平登山口から登ってきた方々だったようなので、「鬼ヶ面山方面から登ってきた」とビシッ!と話したら黄色い声援を多数いただきました(笑)
聞いていると、やはり浅草岳はネズモチ平登山口がメジャールートのようですね。
木道にある休憩ポイント。尾瀬の木道ベンチのようにいくつか休憩スペースが用意されて有難かったです。
こんな感じの尾瀬を思わせる穏やかな湿原。浅草岳山頂はこんな感じの風景が広がってます。
湿原にはワタスゲもちらほら。
ワタスゲと言えば、思い出さずにはいられない田代山湿原。あの湿原を超えるワタスゲの群生は早々お目にかかれないので、比べることはしないけども、あの感動は忘れられず梅雨に見れる花の1つとして自分の中で定着しているワタスゲ。
群生とはいかないまでも、今年もこうして出会えて満足です。
小さいですが池糖もあります。この湿原で休憩しているときは、しばし歩いてきた岩稜を忘れて心底穏やかな世界観に浸ってました。
浅草岳はずいぶん前から狙っていた山で、時期も特にヒメサユリにこだわっていたわけではなく、紅葉としても雪山としても登ってみたい山でした。天気やらタイミングの兼ね合いでこうしてヒメサユリの時期に1発目を登ることになってけども、初夏の浅草岳も素晴らしい景色を見せてくれました。
序盤の岩壁を目の当たりにした辺りでは、ぜひとも紅葉時期にも再訪せねばならないと思った山。岩稜と紅葉のセットは絶対に裏切らないので。
まだまだ隠された魅力がありそうです。
山頂の湿原も十分満喫して下山。来た道を戻ります。
木道から離れて、再び岩稜帯へ。
下山と言ってもこの先もアップダウンがあるので、しっかりと登るシーンもあります。
ピストンというのは来た道をそのまま戻るので本来なら面白みがないけど、今回に限って言えば帰りに天候が回復したので、登って来た時よりもさらなる絶景を拝めることができました。
浅草岳山頂方面から見る、鬼ヶ面山方面の岩稜帯。こちらから見ても断崖絶壁の迫力をまざまざと感じることができます。
アップダウンを前に、ニッコウキスゲが咲いていたお花畑を再び満喫。
本来、ヒメサユリとニッコウキスゲの開花時期はずれるので、こうして両方の花が咲くことが見られたのは本当に幸運だと思う。
何度見ても目を奪われる、この断崖絶壁の稜線。
上信越の山の稜線は穏やかな緑広がるものが多いので、この浅草岳は異端児とも言える。
岩場の多い北アルプスともまた違っていて、これほどの緑を有しながら断崖絶壁が見れるというのはなかなかない。一味違った迫力・魅力を備えてます。
尖った岩の峰。あの先端まで歩くことになるんだぜ!
稜線は実際に歩いているよりも、他の人の歩く姿を見ているほうがスリルある。
雪の浅草岳も登ってはみたいけど、このやせ尾根を見るあたりは六十里登山ルートを歩くのはまず無理だろうな~、、、と思う反面、遠くからでもいいからこの岩壁が雪を覆った姿も見てみたい自分もいたり。
浅草岳も間違いなく再訪するであろう山。それくらい気に入った!
何度となく訪れるアップダウン。細かいのは大して問題なかったけど、奥の北岳の登りはさすがに息が上がりました。
下山とはいえ、ひと山登るくらいの体力は残しておかないとひどい目に合うと思います。
北岳から見た浅草岳。登って来た時よりも鮮明にその姿を捉えることができました。
北岳から鬼ヶ面山へといたる稜線。
来るときには気づかなかったですが、断崖絶壁の稜線はこの先も続いてました。
ここら辺は絶壁の淵を歩いている感じが出てたな~。
下山のほうが見る景色に迫力があって、撮った写真の枚数も多かったです。
ヒメサユリと浅草岳。可憐な花と鋭利な岩稜が正反対の魅力で、これはこれで見ごたえある景色でした。
登山道途中から眺める浅草岳全景。
同じ道でも登ってきた時には見れなかった景色。山頂に湿原広がるとは思えない、荒々しい姿がそこにはありました。
戻るにつれてヒメサユリの数も増してくる。
浅草岳がヒメサユリのメッカとされてますが、正確に言うなら鬼ヶ面山・南岳だと思う。こちらに来ないと群生と呼べるだけのヒメサユリは見れないです。
天気もすっかり晴れて谷底までしっかり見える。
同じ道とは思えないくらい、高度感を感じられた道でした。
改めて振り返って見る浅草岳の稜線。
何度も言うけど、登山道自体は危険個所も大してないので、そこそこの体力さえあれば誰にでも登れるルートです。一度歩いた身としては強く勧めたい六十里登山ルート。
日差しを浴びて、より生き生きと咲くヒメサユリ。
南側から見た浅草岳。北側に湿原が広がっているので、まさにこちらは裏の顔。
険しい山の風格が漂ってます。
片側が切れ落ちた稜線なので、開放感は文句なし。はるか下の谷底まで一望できます。
豪雪地帯ということもあって、6月にしてなお麓にも雪が残ってる。
鬼ヶ面山を越えて南岳へ。登ってくるときには感じなかったけども、南岳もこちらから見ると立派なピークになってます。
何よりヒメサユリの群生が素晴らしい!
南岳山頂直下はヒメサユリロードが続いてます。
絶滅危惧種にも指定されているヒメサユリをこれほど堪能できるとは、なんと贅沢なことか……。日本三百名山、新・花の百名山の称号は得ているけども、浅草岳はもっと評価されるべきだと思う。
こちらがどうしても撮りたかった写真。浅草岳をバックに輝かしいヒメサユリの姿。
見たい景色を全て見ることができて、大満足の山行でした。
最後に南岳から見納めの浅草岳。
残雪の上信越の山は夏前に登りたいと思ってたけども、今年は雪解けが早くて色々と断念した経緯もあったりして……
こうして浅草岳で残雪と緑の絶景を見れて本当に嬉しかったです。
今回はあまり周囲の展望については語らなかったけども、稜線上からは色々な山が見えてました。
中でも注目したのがすぐ近くにそびえていた守門岳。あちらも浅草岳ほどではないですがヒメサユリを見ることができる山です。守門岳については残雪の時期にまずは登りに行きたいので、来年あたりに狙いたいところです。
田子倉湖については南岳からの眺めが一番でした。
ここから見ると良くわかる十字架。こんな珍しい形の湖があるんですね~。
RPGの世界で言えば、あの湖の中央あたりは何かしらのイベントが発生するであろう思わせぶりな形。ここもまた非現実的な世界観でした。
南岳を過ぎれば、あとはひたすら下山するだけ。緩やかな道が続くので楽なもんでした。
途中、ちっこいネズミに出会えたのが印象的。写真に収められなかったのが悔しいけど、野生のネズミってハムスターみたいにちっこくて丸くて可愛いんですね。
都会のドブネズミしかイメージになかったので、ネズミの印象を改めた瞬間でした。
15時20分、駐車場に下山完了。休憩込みで往復8時間程度の山行でした。くっしー、お疲れちゃん!
登り始めは満車の駐車場でしたが、この時間になるとだいぶ減ってました。
下山後の温泉は帰り道にある寿和温泉へ。日帰り入浴は600円。
大浴場と露天風呂が別々になっているので、どちらかを選ぶ必要があります。自分たちはもちろん露天風呂を選んだけど、まさかの貸し切りでした。
洗い場は2つしかないので混雑時はかなり待ちが発生しそうですが、露天風呂自体は広くて快適でした。ドライヤーも完備されているので、ここはぜひ露天風呂に入ってみてください。
温泉にも入って大満足の浅草岳登山。帰りの道路わきに広がっていた魚沼市の田園風景がまた心地よい風景でした。
魚沼コシヒカリはうまい!
……という感じで、今回の旅も終了。
浅草岳はヒメサユリのことに頭がいっぱいで、登山道については詳しく調べていなかったけど、そのおかげもあって前評判を大きく覆す感動が得られました。
鋭利な岩稜が続く六十里登山ルートの稜線。この断崖絶壁の風景は上信越の山ではそう簡単にお目にかかれないものだと思います。岩の名所の八海山でもこれほどの絶壁は見れなかったので、越後の山の中でもかなり特殊な山容の浅草岳。
ぜひ訪れてほしいところです。
今回は六十里登山ルートを紹介しましたが、メジャーなネズモチ平ルートでも楽しい山行になると思います。浅草岳本来は湿原広がる穏やかな山なので、それを堪能するならむしろネズモチ平登山口からのほうが木道歩きが続くので良いのかもしれません。
ただヒメサユリが目的なら、一番の群生は南岳~鬼ヶ面山にかけての稜線なので、ぜひ六十里登山口から歩くべき。アップダウン多いですが、日帰り登山としては十分に歩き応えもあって、充実した山旅になること間違いなしです。
ヒメサユリ天国が広がる浅草岳、紅葉も雪山も綺麗と聞くので、季節を変えてぜひまた再訪しようと思います。
本当に素晴らしい山でした!
(一緒に登ってくれたくっしー、ありがとさん!)
ヒメサユリ咲き誇る浅草岳―――
おしまい
【日程】
2016年6月18日 曇りのち晴れ
【コースタイム】
六十里登山口(7:30) — 南岳(9:00) — 鬼ヶ面山(9:40) — 北岳(10:00) — 浅草岳(11:30~12:20) — 北岳(13:15) — 南岳(14:15) — 六十里登山口(15:20)
Copyright © 2016 今日という日を忘れずに All Rights Reserved.