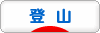2017年最初の山登り、南アルプスの女王・仙丈ヶ岳へ。
1日目に戸台口駐車場から長い河原歩きを経て山小屋「こもれび山荘」に到着。2日目にいよいよ仙丈ヶ岳の山頂へと向かいます。山小屋から山頂までの往復だけなので、行程としてはそれほど長くはないですが、それでも目指す場所は3000mを越える高峰。森林限界を超えてからは油断ならない狭き雪の稜線が続きます。
登頂できたかはさして重要なことではなく、それよりも小仙丈ヶ岳まで登った先に待っていた白き仙丈ヶ岳の姿にただただ感動!横を見れば富士山~北岳~間ノ岳と日本のトップ3が並んでおり、新年早々素晴らしい景色に出会えた1日でした。
華やかな幕開けとなった2017年最初の登山、後半戦。
南アルプスの女王・冬の仙丈ヶ岳の頂目指して―――
(前編からの続き)
1日目に戸台口駐車場をスタートして、北沢峠のこもれび山荘に宿泊。美味しい夕食を頂いて英気を養い、翌日いよいよ仙丈ヶ岳山頂を目指します。
すでに1日目の段階で標高1000m以上は登ってきてますが、それでもまだ標高2000m地点。2日目の登山は山小屋から山頂までの往復なので行程としてはそこまで長くはないけども、標高差1000mは登らないといけないので油断ならない。場所が3000m峰の雪山と考えたらなおさら。
前日にそこまで疲れがなかったのもあるけど、翌日への不安と期待が入り混じった興奮もあってなかなか寝付けずに夜を過ごし、そして迎えた2日目の朝。
ここから後半のお話の始まり。
~~ 2017年1月5日~7日 仙丈ヶ岳(2日目) ~~
2日目の行程については、暗いうちからスタートして森林限界を超えたあたりでご来光でも見ようかと思ったりもしたけど、今回は時間だけはたっぷりあるのでそこまで急ぐ必要もないし、早朝はまだ暴風予報が出ていたので、明るくなってから出発することにしました。
こもれび山荘は携帯の電波は届かないですが、ヤマテンの予報を張り出してくれるので助かります。
2日目の朝食。ここの夕食は豪勢だけど、朝食はまぁ普通か。こもれび山荘は1泊夕食付で泊まるのが最も賢い選択かもしれないです。朝食頼まなければ、出発の時間を自分でコントロールできるしね。
5時に起きる予定だったのに、中途半端な二度寝でまさかの寝坊。これも正月ボケのせいだ、きっと……
この日は山頂から降りてきてまたここに泊まるので、不要な荷物は全部置いていけるという特典付き。行程も夏の標準タイムで7時間弱なので、余程のことがない限りは時間に追われることもなさそう。
ゆっくり準備して、空が十分に明るくなってきた7時頃に小屋を出ました。ちょうど山岳会の方たちが下山するところだったので、ここでお別れ。この日山登りをしてこの小屋に戻ってくるのは自分以外にソロの方2名で、1人は甲斐駒ヶ岳、もう1人は自分と同じく仙丈ヶ岳を目指すそうです。
朝7時、こちらの山荘前トイレ脇の登山口からスタート。例年に比べると雪が少ないとはいえ、ここまで来ればそれなりの積雪量だったので、最初から12本アイゼン履いちゃいました。
しばらくは樹林帯の中を黙々と登って行く。登山口から1合目、2合目とカウントが始まるので良い目印にもなります。
樹林帯の中からではあったものの、森の中から迎えた日の出が綺麗でした。
途中はすっ飛ばして、1時間20分ほどで4合目に到着。この日は午後になるほど気象条件が良くなるってことなので、かなりスローペースで登ってます。
展望が良くなるのは6合目から。もし暗いうちに山荘を出発して朝日を見たいなら、ご来光の2時間前には小屋を出ておく必要がありそうです。
登るにつれて積雪量も増えてくるけど、正月の間に踏み固められたトレースがバッチリあるので難なく歩けます。
予想以上に暖かく、牛歩ペースの割に結構汗かきました。
8時50分、大滝ノ頭に到着。ここが5合目になります。
夏場であればここが馬の背ヒュッテ方面との分岐点でもありますが、冬の時期は選択肢としては1つしかなく、このまま直進して小仙丈ヶ岳を目指すのみ。
このあたりに差し掛かると、展望もチラホラ開けてきます。
東側に見えていたのが甲斐駒ヶ岳とアサヨ峰。いまだ樹林帯ではあるものの標高は2500m付近。見れる景色のスケールはでかい。
アサヨ峰からさらに南に視線をずらすと、鳳凰三山も見えました。槍のようにぴょこんと突き出た地蔵岳のオベリスクが目立ちます。
鳳凰三山は南アルプス界隈でも特に雪が少なかったです。
5合目から先がいよいよ面白くなってくるところ。
気づけば見渡す空も広くなって、いつの間にか森林限界を迎えていました。
ここまで来たらもう展望ラッシュ!目の前には仙丈ヶ岳の迎えに聳える甲斐駒ヶ岳を一望!その左奥には八ヶ岳も見えてきました。
※ここから先、進むペースに比べて写真の枚数が飛躍的に増すと思うので、適当に読み流してくださいm(__)m
こちらは南アルプスの中では屈指の岩山ともいえる鋸岳。1日目の河原歩きの最中、頻繁にその名を目にした山の正体がこちら。
仙丈ヶ岳穏やかな山容とは真逆の、ゴツゴツした凹凸の稜線が見えました。
今回のスタート地点となった戸台口は、本来であればあの山を登るための登山口。
周囲の名峰に舌鼓を打ちながら、目指す先にもそそられる雪の稜線が現れてくる。
樹林帯を越えていきなりこの景色。世界観がガラリと変わります。
そんな中にあったのが6合目。ここまで登ってきてしまえば、周囲を覆う樹々もなくなります。
逆に言うと、風が強い場合はここから先は逃げ場がないので、この手前で装備を整えておく必要あり。この日に限って言えば、ここでピッケルにこそ持ち替えましたが、オーバーグローブが不要なほど快晴無風で、この時期にしては奇跡的なほどの穏やかな陽気でした。
視線の先には、早く飛び込みたくなるような雪の道。空の青と雪の白さが絶妙に綺麗でした。
良く見ると前方にお二人先行者を発見。この方たちは、1日目に八丁坂付近で自分が追い抜いたテント泊の女性2人組でした。
後ろを振り返ればドーン!と甲斐駒ヶ岳。この日は登山史上、最もカメラのシャッター回数が多かった一日だったかもしれない。
同じような写真を大量に撮ってしまいましたが、それくらい絶景が続いてた冬の仙丈ヶ岳。(この先はさらに写真の撮影枚数が多かったので、整理するのに苦労したぜ……)
正面に見えるのは仙丈ヶ岳手前の小仙丈ヶ岳。南アルプス女王の娘さんも何とも美しい山容してます。
穏やかな山容ではあっても、傾斜は部分的には急なところもあります。
それでもトレースがはっきりとついているので、一部クラスト状になっているのを除けばとても歩きやすい。
ここをラッセルなんて言ったら、さぞキツそう……
う~む、何度も振り返ってしまう甲斐駒ヶ岳。カッコいいよ、ホント。
後ろにお一人登山者が見えますが、この方は自分と3日間全く同じ行程で山小屋に泊まっていたソロの方。この方もおそらく時間を持て余さないようゆっくり歩いていたのもあって、山小屋のスタートから下山までほぼ同じペースで歩いてました。
ここら辺まで登ってくると良く見えるようになるのが西側の北アルプスの山並み。一番左に見えるのは乗鞍岳(3026m)。2年前の冬に雪山登山として登りに行った初の3000m峰があの山でしたが、あの時もコンディションに恵まれて絶景を見れた山登りでした。
雪の残っている時期としては、他にGWに北穂高岳や槍ヶ岳なんかに登ったりもしたけど、この厳冬期には到底登れる気がしない。今の自分の力量としては、冬に3000m峰に登るなら「山小屋あり×トレースあり×天気最高」の3拍子が揃わないとおそらく無理だな。
それを自覚しているからこその今回の仙丈ヶ岳。複数の山サイトの天気予報がすべて快晴予報を出し、かつ正月休み明けというトレース泥棒を大いに期待できる企みがあってのこのプラン( ̄ー ̄)ニヤリ
まぁ、あの小仙丈ヶ岳まで登ってしまえば、自分が雑誌で目にした見たい景色は見れるので、最悪コンディション次第では無理せずにあそこで終わりにしたって仕方ないとも思ってもいた。
そう思ってはいたものの、やっぱり来たからには山頂を踏んでおきたいという気持ちも当然あったりして……
この当たりに差し掛かると風も完全に収まったので、ピークハントが現実味を帯びてきたところでもありました。
登っている間は稜線の美しさに心奪われてるけど、後ろを振り返ってみると現実に引き戻される。
写真では良く伝わらないですが、実際にその場に立つ雪の傾斜がえぐい所もあったりします。
ずっと急斜面が続くわけでもないので、ひとたび穏やかな稜線に出れば心行くまで景色を楽しめる。
小仙丈ヶ岳の先にどんな景色が待っているのか、色々と思いを馳せる楽しい時間でした。
さらに登った先に見えてきたのが中央アルプスの山々。
山頂に行けばより一層はっきり見えるのはわかっていたけど、手前で見えてしまったんだから仕方ない。立ち止まって写真を撮りまくる。
こうして10時ちょうど、小仙丈ヶ岳に到着。
誰かが掘り起こしたのか、ギリギリ標識は見えてる状態でした。
そしてこの小仙丈ヶ岳が、本ルート屈指の展望台ともいえる場所。山頂以上に長居してしまったところでもありました。
まず南側に見えたのが、こちらの日本のTop3!標高No1の富士山、No2の北岳、No3の間ノ岳。
このトップスリーを綺麗に横並びに見れるのが小仙丈ヶ岳。
No1(富士山)とNo2(北岳)の共演。
一般的な正月期間は仕事もあったりして、なかなか山登りをする時間もなく。。結局この瞬間が、2017年の初富士となりました。
こちらは南アルプス南部の山々。中央にでかく聳えるのが塩見岳になるのかな。
あちらの山々も標高3000mを超える立派な高峰たち。1つ1つの存在感が際立ってました。
そしてこちらが冬の仙丈ヶ岳。
雪を纏った白き女王の姿、これがまさに見たかった景色!
待ちに待った瞬間。感動以外の言葉が見つからない素晴らしい景色!
目の前に広がる広大な雪の斜面は小仙丈沢カール。ここからは見えないですが、稜線の反対側には大仙丈沢カールも広がってます。
見事な曲線美のカール、これこそが『南アルプスの女王』と称される所以。
長い河原歩きをしてまで登ってきたのは、この景色を見たいがため。山頂に行かずとも、この瞬間に苦労が報われました。
北アルプスも南の乗鞍岳から北の白馬岳まで、全域を見渡せるようになりました。
あまりにも素晴らしい景色だったので、小仙丈ヶ岳でしばらく休憩。時間に余裕があるので、心行くまで冬の仙丈ヶ岳を楽しむ!
休んでいたら小屋で一緒だったソロの方が登られてきたので、記念に1枚撮ってもらいました。
本当に見事な雪景色!無風で気温もそこまで低くなかったので、座って休んでも全然身体が冷えずにいられたのも良かった。
最高の時間でした。
下をのぞくと馬の背ヒュッテが見えました。
この先、切り立ったような道が続くので、周りの景観と同様に足元も良く見通せるようになってきます。
……いや、見通せるようになってきてしまいます(汗
小仙丈ヶ岳でしばし展望を楽しんで先へ。
この先から、いよいよ仙丈ヶ岳の核心部と言われている場所に入っていきます。
まずはこの進むにつれて狭くなっていく細い稜線。
傍から見るとナイフリッジのようにも見えるけど、実際に歩いてみると割と幅に余裕があるので、そこまで危険には感じなかったです。風もなかったし。
カールと合わせて稜線もこの見事な曲線美。 写真を撮る手が止まらない。
ここを暴風の中進もうとしたら、恐怖の平均台と化すのかもしれないけれど、無風という恵まれたコンディションなのでアイゼンひっかけて転ばない限りは、何ら通過は問題なかったです。
適度に雪も引き締まってアイゼンも良く効いてくれました。
進むたびに現れる雪の造形に見惚れて、なかなか足が進まない。
このアングルの仙丈ヶ岳が本当に素晴らしい!例年に比べたら雪は少ないらしいけど、景観としては十分見応えある雪景色でした。
雪山を初めて間もないころに冬の仙丈ヶ岳を知って、ずっとこの景色に憧れてたんだよな……。
実際に歩いているところを見るとこんな感じ。
一人分の幅しか確保されてない細い道。実際に歩いている分には怖さはなかったけど、こうして他の人が歩いているのを見る方が怖く感じる。
ずっと細い道が続くわけでもなく、適宜休憩ポイントのように開けた場所もあるので、休みながら歩けます。
仙丈ヶ岳は夏場に2回登りに来てるけど、記憶があいまいで特に小仙丈ヶ岳から先の道がどうなっていたかいまいち覚えていなかった。(夏もあんなに細い道だったっけか……?)
見たところトレースがバッチリついているので有り難くそれをなぞらせてもらいます。
この時点で稜線上にいるのは前方の女性二人組と後ろのソロの方と自分の4人だけ。これだけの景色を静かな中で堪能できる、最高に贅沢な2017年の正月休みです。
10時50分、八合目に到着。
ここから道はいったん広くなって、斜面をガツガツ登って行きます。
そういえば八合目で思い出したけど、1日目にすれ違った小学生の女の子は暴風の中ここまで来たのか!?あの細い稜線を突破したとは、なんとも素晴らしいこと。身体も軽いから大人以上に風の影響も強いだろうし、ひたむきに前に進んでいる姿が容易に想像つきます。
それに反してこのみやっちという男は何なんでしょうね。快晴無風狙い&トレース泥棒をしている自分が恥ずかしいことこの上ないぜ……
あまりのベストコンディションに申し訳なくもなるけど、やっぱり天気が良いのは大事。空の深いブルーと雪景色が本当に綺麗でした。
3000m地点にいることを忘れるくらいの暖かさ。紫外線が強烈で、日焼け止めは必須でした。
写真を適当にパラパラと。
ここら辺は条件が良ければ立派な雪庇が出来上がるところなんだけど、この時点ではまだ雪庇と呼べるほどには育っていませんでした。
まぁ雪庇が育つ頃には、到底自分一人の力量で登れるコンディションではないんだろうけどね。。
6合目あたりからずっと見えている北アルプス。この日はあちらも終日快晴で登山日和だったようです。
カールの淵に沿って登って行く。
終点も見えてきましたが、このまま稜線沿いに進むわけではないです。
山頂付近に差し掛かるとカールとは反対側の斜面へ回り込みます。
ここら辺は岩が露出していたり、アイゼンが効きにくいほど凍結していたり、少し怖かった箇所。
そしてここに来てはっきりと見えた仙丈ヶ岳山頂。一番右の背の高い所がピークになります。
こちらにも美しいカールが広がる景色。冬の仙丈ヶ岳はどこを切り取ってみても絶景です。

狭い尾根よりも一番緊張したのがこのトラバース箇所で、雪が少なくて氷に近い状態だったので足元が滑らないか不安でした。
ピッケルの支えが最も心強く感じたところ。
下に見えたのが仙丈小屋。
足元を滑らせるとあそこまで一気に落ちてしまうので要注意ポイント。

トラバースを過ぎて短い斜面を登れば、最後の稜線部。
2つのコブを越えて行けば山頂に到着しますが、あそこもなかなか細い道になってます。
白き稜線を行く冬の空中散歩。
前を歩く二人組の姿がカッコいい。自分で歩いている分には感じないけど、こうして他の方が歩いているのを見ると、すごい場所にいるんだなと実感します。
ちなみに前を歩く二人が女性と知ったのは山頂に着いてから。ずっと自分の前を勇ましい姿で歩いているので勝手に男性だと思い込んでました。
ラストもナイフリッジに近い狭い道となるので気は抜けない。
ここら辺はさすが3000m峰と言えるしたたかさを見せてきて、適度な緊張感がある局面でした。
こちらが先ほどのトラバース箇所。見た目は大した事なさそうに見えるけど、ここが一番神経使ったところ。雪がもう少しついてくれてたら良かったんだけど、氷に近い状態だったので通過するのに難儀しました。
小屋に戻って写真に写っている男性とも話しましたが、やはりここが一番怖い箇所だったようです。
ゴジラの背のようなコブを越えて山頂へ。
ここら辺もトレースあるから難なく進めるけど、手探りで行けって言われたらなかなかの難易度だったと思う。
道の狭さでいったら、ここが最狭・最細だったかな。これはナイフリッジと言ってもいいくらいの平均台でした。
両側が切り立っているので、足元もスッカスカ。展望だけはやたらといい道です。
上から見下ろす仙丈ヶ岳のカール。メローな雪の傾斜に見惚れてばかり。
冬の南アルプスの女王に心底惚れこんでしまったので、こうなってくると冬の北アルプスの女王・燕岳にも手を出したくなってくるところ。
山頂への最後の登り。短いから良かったけど、この斜度はなかなかのものでした。
おそらく今回の行程で一番の急斜面。最後まで手厳しい女王。
11時30分、仙丈ヶ岳山頂に無事に到着。
2017年1発目でいきなり3000m越え。少し欲張りすぎな気もするけど、華々しい幕開けとなりました。
今年も年間通じて良い山登りがしたいものです。
山頂からすぐ正面に見えていたのが中央アルプス。伊那市を挟んで木曽駒ヶ岳などの山々が綺麗に見えました。
さらによく見ると、中央アルプスの背後に御嶽山、さらに右奥に見える真っ白な山は、おそらく白山。どこもかしこも天気が良いようで、仙丈ヶ岳から見え得る距離の山域はすべて見えました。
南アルプス南部の山々。昨年の夏に聖岳~光岳をやり遂げて、南アルプスの有名どころは一巡したけど、季節やルートを変えて登りたいところはまだまだ多い。
改めてこちらは日本のトップ3、富士山~北岳~間ノ岳。少し遅くなったけど新年の初富士も無事に見れたし、万々歳の内容。
金も結構使ったけど、正月の休出手当をつぎ込んだと思えば差し引きゼロ。やや鳴り物入り感の突発的な決行ではありましたが、仙丈ヶ岳を選んで本当に良かったです。
こちらはお隣の甲斐駒ヶ岳。女性的な仙丈ヶ岳に対して、岩のゴツゴツ感が引き立つ男性的な山。岩も結構露出して、仙丈ヶ岳よりも積雪は少なそうでした。
冬の甲斐駒ヶ岳に関しては、北沢峠側からよりも黒戸尾根を登ってくる人の方が多い印象。黒戸尾根自体まだ一度も歩いたことがないので、いつか一度は登ってみたいところです。
南アルプス鋸岳。その背後には八ヶ岳、さらにその後ろには浅間山、写真では見切れているけど左奥には北信エリアの山々もバッチリ見えました。
八ヶ岳はこの時点では全然雪が少なかったけども、この翌週に待望の寒波到来で大雪を降らせてくれました。実際、この仙丈ヶ岳の次の登山があちらの八ヶ岳になったのですが、そこでも結構な雪景色を堪能できました。
北アルプスの白さは相変わらず。本当なら1月の3連休に北アルプスに入る予定だったのですが、悪天候で願いかなわず。
厳冬期にこれだけ1日中安定して晴れている北アルプスも珍しいと思う。
ソロの方も到着して、この日に僕と同じタイミングで登っていたのはこの3人だけ。
世間は正月休み明けの平日なので、最悪誰もいないんじゃないかって思ってたけど、適度に人がいてくれて良かったです。雪山に限らず混雑は嫌いだけど、他に登山者がいると少なからず安心するのもあるし。
しばらく山頂で展望を楽しんでから下山開始。展望は良かったけど、個人的には小仙丈ヶ岳からの景色が一番だったので、あちらまで戻ってまた休憩することにしました。
山頂直下の急斜面は、やはり上から見るとなかなかの高度感があります。
帰りも細い雪の平均台を歩いていく。
トラバース路から振り返ってみる仙丈ヶ岳。小仙丈ヶ岳まで戻るともうこの景色は見れなくなるので、しっかりと焼き付けておく。
冬の白き女王はとてつもなく美しい山でした。

再び小仙丈のカール側に出る。
再び見えてきた小仙丈沢カール。何度見ても美しい。
朝に見た時よりも陽の位置が変わったので、雰囲気も若干違って見えます。
仙丈ヶ岳の白き稜線、空中散歩をしているかのように空との距離が物凄く近く感じます。
何度も振り返ってしまうこの景色、おそらく一生忘れないんじゃないかってくらい心に響いた絶景でした。

小仙丈ヶ岳まで戻ってきたのが13時頃。この時間に山頂を目指す方もおりました。
下山途中にすれ違ったのもソロの方3人だけ。結局この日に仙丈ヶ岳に登っていたのは10人にも満たない閑散とした1日でした。
急いで小屋に戻ってもすることがないので、小仙丈ヶ岳で時間を潰す。登っている山自体はなかなかの標高だけども、プランとしては正月らしい緩いスケジュール。これほど時間を持て余す行程を組んだのは久しぶりだったけど、これくらいゆとりあるのもたまには悪くないと思いました。

小仙丈ヶ岳から下るとすぐに樹林帯に入って展望がなくなるので、富士山もここで見納めしておく。
当然ではあるけども、距離的な近さもあってNo2の北岳の存在感のほうが圧倒的でした。
陽が西に傾き始めると、山の雰囲気も一気に変わる。
やや赤みを帯びた冬の仙丈ヶ岳も美人さんでした。
名残惜しいけど、暗くなるまでいるわけにもいかないので小仙丈ヶ岳から下山。
1日を通して穏やかに微笑んでくれた南アルプスの女王・仙丈ヶ岳。絶対にまたいつか来ます。
夕暮れ時の小仙丈ヶ岳。最高の景色を見せてくれたあの山にも感謝。
夕焼けに染まる北岳。
一日穏やかな中で登山を楽しめた最高の1日。見たい景色はすべて見ることができました。
樹林帯に入ってから先は速かったです。雪がある方が下山は楽な気がします。
こうしてメインの2日目の登山行程が終了。
宿に戻ってきたのが15時過ぎ。7時に小屋を出発したので、みっちり8時間費やして冬の仙丈ヶ岳を楽しめました。
早い人なら、早朝から仙丈ヶ岳に登って、そのまま戸台口へ下山することも可能だと思います。
小屋では昨日とは人が入れ替わり、人数も若干増えてました。まだ金曜日だったので人数が増えたのは少し意外。
それでも15人ほどで、使われてない布団の方が多かったくらいです。
こちらが2日目の夕食。カレーとフライの盛り合わせ。
前日のハンバーグも良かったけど、2日目も山小屋の食事とは思えないほど豪勢。翌日は下山するだけという気楽さもあったので、ガッツリ頂きました。
1日目と同じく宿泊客みんなでテーブルを囲んでの食事。ほとんどの方が翌日仙丈ヶ岳に登るので、コンディションなんか色々と聞かれたけど、とりあえず「小仙丈ヶ岳からの展望が最高!」と言っておきました。
こうして楽しい2日目が終了。
3日目は下山するだけですが、せっかくなので少しだけ書いておきます。
~~ 2017年1月5日~7日 仙丈ヶ岳(3日目) ~~
1月7日の朝5時に起床。2日目の山頂アタックの興奮が冷めやらぬ状態だったからなのか、この日もそんなに寝付けませんでした。
高速バスではのび太並みに一瞬で眠れるのに、こういう場所で寝れなくなるのは自分でもよくわからないんだ……。
3日目の朝ごはんはまさかのおでん(笑)
独り暮らしをする上で、大量作り込みは経済的なので冬は良くおでんを作ったりする。自分のおでんにはソーセージとニンジンを加えるので、この具材のラインナップはやや不満でした。
全然関係ないけど、煮込み系を作る上でシャトルシェフは便利なのでおすすめ。
他の方たちが仙丈ヶ岳へ足早に出発する中、自分は下山するだけなのでゆっくり準備。昨日同じペースで歩いたソロの方も今日は下山するだけだったので、小屋でのんびり過ごしてました。
朝7時に3日間お世話になった小屋のスタッフさんに挨拶して、山小屋を出発。
戸台口駐車場までの長い道のりを戻っていきます。
八丁坂の急登も下りはあっという間。小屋から1時間程度で河原歩き入口の丸太橋まで降りてきました。
この日も絶好調な具合に凍結してましたよ。
再び長い河原歩きが始まる。まだ河原までは日が差し込まない時間帯。
やや肌寒かったです。
この日から世間は3連休。あいにく翌日から天候が悪くなる予報でしたが、登ってくる登山者の数は多かったです。団体さんが多く、中にはテレビでも見たことある有名なガイドさんもいました。
僕が泊まった「こもれび山荘」も、冬季の営業はこの3連休でおしまい。冬の仙丈ヶ岳へ山小屋泊で登りに来るなら、チャンスは年末年始にかけての2週間ほどしかないのでご注意ください。
1日目に見た廃墟感漂う古いダム。
こういう平坦な道は帰りの方が長く感じるっていうけど、この日は初日と違ってたくさんの人とすれ違って、上の状況を色々と聞かれたりもしたので、不思議とあっという間でした。
渡渉も登りに来た時とは全然別の箇所で渡った。どっちが正しい道なのかわからないけど、ようは突っ切れそうなところを渡ってしまえばOK。
こうして朝10時に戸台口駐車場に無事に帰還。
ここから仙流荘まで行くなら、さらに1時間ほど歩くことになります。
下山後の温泉は高遠のさくらの湯へ。仙流荘でも入浴はできるけど、バスの時間との兼ね合いからこっちにしました。
ここまで来てしまえば路線バス1本で伊那市駅まで戻ることができます。
温泉でさっぱり汗を流してJR伊那市駅に到着。電車を使って都内へ戻るのは時間もお金もかかるので、帰りも高速バスを利用。3連休の初日は高速バスもがら空きなので、それも嬉しい所だったりします。
こうして3日間の南アルプス仙丈ヶ岳の山登りが終わりました。
もう絶景の連続で言うことなしの内容。特に小仙丈ヶ岳から先は、足が全然進まなくなるほどの素晴らしい景観!中でも特に見たかったのが雪の仙丈ヶ岳のカール。
写真でしか見たことなかったけど、実際に目の当たりにしてその美しさにただただ感銘を受けました。
冬の仙丈ヶ岳は序盤の河原歩きが長いので、自分もそこだけやや敬遠してたけども、個人的な感想としては言うほどの長さは感じなかったかな~という印象です。ただの林道歩きというわけでもなく、渡渉ポイントを見つけなきゃいけなかったりと割と神経使ったからかもしれません。真っ暗だとかなり迷いやすいと思うのでそこだけご注意ください。
2017年1発目の登山としては、華々しい幕開けができたんじゃないかなと思っている今回の仙丈ヶ岳。白き雪の女王は惚れ惚れするほどの美しい姿で、自分の雪山登山史の中でも思い出深い1ページができました。
2017年はこの後もすでに2回ほど雪山登山を終えているので、また気が向いたらブログ更新していこうと思います。
だいぶ長い記事になってしまいましたが、ここまで辛抱強く読んでくださった方、ありがとうございましたm(__)m

2017年正月、冬の仙丈ヶ岳より―――
おしまい
【日程】
2017年1月5日~7日 全日快晴
【コースタイム】
・2日目
こもれび山荘(6:50) — 大滝ノ頭・五合目(8:50) — 小仙丈ヶ岳(10:10) — 仙丈ヶ岳(11:30~12:00) — 小仙丈ヶ岳(12:50~13:40) — こもれび山荘(15:00)
・3日目
こもれび山荘(7:00) — 丹渓山荘跡(8:00) — 戸台口駐車場(10:00)
Copyright © 2017 今日という日を忘れずに All Rights Reserved.