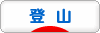新潟県の守門岳(すもんだけ)へ登ってきました。
冬の守門岳は山頂稜線に作り上げられる大雪庇が有名で、その大きさは東洋一と謳われるほど。今年は例年に比べると雪も多かったようで、想像以上に立派な雪庇が出来上がっていました。
青空の下に輝く白く滑らかな稜線も美しく、さらに前日までの雪のおかげで、登山道には見事なほどの樹氷群!スノーモンスターに近いものもあって、雪庇と合わせて楽しむことができました。
越後三山や尾瀬、妙高山や飯豊山など新潟近隣の山も見渡せて、今シーズンの雪山登山の締めくくりに相応しい山登りができた1日でした。
東洋一の大雪庇、新潟県の守門岳へ―――
新潟県の「守門岳」(すもんだけ、標高1537m)。
日本二百名山の1つであり、かつ新・花の百名山にも選ばれている花の名峰。初夏の時期に咲き誇る稜線上のお花畑も魅力的ですが、この山は雪山としても大変人気が高く、その理由が稜線に広がる東洋一とも言われている大雪庇。
上信越ならではの冬の厳しい環境下によって作り上げらえる巨大な雪の造形。見ることのできる期間はだいたい遅くても4月上旬あたりまで。真冬は天候が安定しないので、なかなかチャンスが巡ってこなかったですが、今年は意外にも3月中旬に快晴予報が出て、休みとも重なったので、満を持して行ってきました。
結果的には、この守門岳が今シーズンの本格的な雪山登山としてはラストになったのですが、最後を締めるに相応しい景色に出会えた1日となりました。
2017年3月12日 守門岳 日帰り雪山登山
冬の守門岳に登る場合、ルートはいくつかありますが、最も登られているコースが今回自分たちが利用した「保久礼コース」になるかと思います。
ただ夏場利用できる駐車場までは積雪による道路封鎖で行くことができないので、手前の二分橋付近の最終除雪ポイントからのスタートとなります。
こちらがそのスタート地点。最終除雪地点には駐車場もありますが、数台くらいしか停められないので、大半はこんな形で路上に縦列駐車することになります。
この日は滅多にない快晴予報が出ていたのもあって、かなりの登山客が入ってました。
自分たちは6時半ごろに現地入り。最終除雪ポイントの200mくらい手前のスペースに車を停めましたが、これでもまだ登山口に近い方だったと思います。
7時過ぎに必要な装備を抱えて登山口へ。身長を超える積雪を眺めながら雪の回廊を歩いていきます。
今回は久しぶりにくっしー先生にご同行頂くことにm(__)m
去年の6月に浅草岳を一緒に登った時に、冬の守門岳もご一緒しようかって話になってそれがようやく実現。浅草岳から守門岳は距離的にも近く、下山後の温泉も同じ所になりました。
最終除雪ポイントが冬の守門岳・保久礼コースの登山口。登山口でスノーシューを履いていざ雪原へ。
遠くに見える白い山が守門岳。目指す先は遠く、夏場の登山口よりもかなり手前からのスタートになるので、まずはその距離を縮めていきます。
コンディションによってはスノーシューがなくても登れますが、雪庇の時期はまだ雪がたっぷり積もっているのでつぼ足だとややきついかもしれません。
この日もほとんどの人がスノーシューやスキーを履いて登っていました。逆にアイゼン・ピッケルは出番なし。
先行者たちが作ってくれた道に沿って進んでいく。
風がなく、朝から暖かい1日でした。
樹林帯に入ってから多少の登りはありますが、まだ序盤は緩やか。
まず目指すのは夏場の登山口になっている保久礼小屋。そこまでは比較的楽な道が続きます。
冬場は無駄に歩かなきゃいけないけど、この序盤の林間コースは個人的にはかなり気に入ったところ。
クリスマスツリーが立ち並んでいるような、独特の冬の森の雰囲気が出てたし、そこまで視界も遮られていないので展望も楽しみながら歩けます。
目指す守門岳はまだまだ遠いけど、この序盤は単なるスノーシューハイクだけでも楽しめそうなところでした。
行きは全然苦にならなかった。帰りは長く感じたけど……
真っ白い雪を被った守門岳。
雪庇はこちらとは反対側にできているので、ここからではこんもりとした丸い山容の山にしか見えないです。
朝日が差し込む守門の森。
青空の下に広がる森の雪景色は美しく、また進むにつれて新たな絶景も見えてくる。
樹々の合間から見えた見事な雪山。奥に見える大きい山は越後三山。左の尖がったのが越後駒ヶ岳、右の平らに見える山が八海山。中ノ岳は越後駒ヶ岳と重なってこの位置からだと見えない。
白馬界隈の北アルプスの山にさえ匹敵する白さと険しさがありました。手前の山なんて標高1000mにも満たない山だろうけど、立派な雪山になってます。さすが日本屈指の豪雪地帯。
景色もコースも一級品で、雪庇を前にすでに上機嫌!
久しぶりのスノーシューということもあって、道を外して好き放題踏み荒らすぜ~
スノーシュー履いていてもこれくらいは埋まるので、かなり新雪フカフカのコンディションでした。
横を見ると綺麗に残ったウサギのかわいい足跡。
この積雪でも埋まらない跳躍力がほしい。
道はいまだに平坦。ひたすら守門岳との距離を縮めていく。
駐車場から2時間ほど歩いて保久礼小屋に到着。こんもりと白い大きな帽子を被ってました。
夏はこの手前まで車で入ることができるので、冬場はここまでの2時間を余分に歩かないといけないわけですが、なかなか良い景色を見せてもらったのでそこまで苦でもなかったです。
ここで小休憩して、先へ進む。ここからいよいよ登山本番といったところで、いきなり急登が控えています。長く緩やかな道が続いて身体は十分に暖まったので、タイミングとしてはちょうどいい。
この急坂の直登はしばらく続きますが、上に行くにつれて景色も一変。
白銀という言葉がピッタリの樹氷の世界が広がり始めました。
これも降雪直後の恩恵。
霧氷と樹氷が合わさった素晴らしく上品な景観。急登もこの景色を楽しみながら登れれば、大して疲れない。
40分ほど登ると樹々の位置も低くなり、視界が開けてくる。
このあたりにキビタキ避難小屋があるはずだったんだけども、気づかずに通過してしまいました。
さらに登ると樹氷が成長して、スノーモンスターになりかけのものも出てくる。
枝の形が残る鋭利なモンスターは森吉山で見たそれとはまた違った雰囲気があります。キリッとしていてカッコいい。
さらに登り進めると周りを覆う樹木はほとんどなくなって、あたりは雪原に変わっていきます。
下から見えていた白く禿げた部分にようやくたどり着いた。
後ろを振り返ればご覧の展望。
雪国なだけあって、街中まで見渡す限りの雪景色。
樹氷のゲートをくぐっていく。
降雪直後の雪山は登るのも一苦労だけど、それ相応の絶景が見れるから頑張れます。
全然関係ないけど、守門岳って「守る門」って書くから、勝手にディフェンス・ゲートって命名して、それ連呼しながら登ってたな…
雪の不思議なモニュメント。
これも自然の芸術。色々と面白いものを見せてくれるから登山はやめられない。
この景色もまた良かった。
冬に見ることのできる雪景色が目いっぱい詰まった壮観な眺め。樹氷と、その奥に聳える上信越を代表する白き越後三山。この位置まで来ると、中ノ岳も越後駒ヶ岳の陰から顔を出すように見えてきました。標高はアルプスには到底及ばないけども、雪を被ったその姿は何ら引けを取らない迫力。
新潟も登りたい山はまだまだたくさんある。
山頂までのビクトリーロード。
一面真っ白な雪の斜面。目標物がないだけに意外と時間がかかるけど、周りを見渡せば絶景に浸れるので最高に楽しいひと時。
常に目が行ってしまう越後三山の雪景色。
贅沢すぎるロケーション。
こちらは反対側の景色。目の前に見えている尾根が赤花コースの登山道。
何ともメローな斜面が広がっていて、あちら側をスキーで滑っている人も何人かいました。
長岡市街を見渡すこの景観も見逃せない。
急登を登ってきたが故に、標高1500m足らずでも非常に高度感があります。
良く見ると、遠くに薄っすらと聳える白き山脈を確認。
こちらは妙高山・火打山の山域。まるで空に浮いているようにさえ見える姿。改めて思う、新潟の雪景色の壮大さ。
樹氷も完全になくなり、山頂まで一直線の雪原ロードに入る。
目指す山頂もはっきりと見えてきました。
ふと上を見上げたら、太陽の周りに綺麗な虹の輪っかができてました。
日暈と呼ばれるもので、一般的にこれが現れると天気が下り坂と言われていますが、この日に関しては午後になるにつれて天気も良くなっていきました。
越後三山をバックにくっしー先生の絵になる姿。
ボードを担いで登る姿がまたカッコいいっすね。
日暈の虹が照らす守門岳の山肌。奇跡的なまでに恵まれた天候で、目にする全てが美しい景色。
何枚も写真に納めてしまった越後三山と樹氷の景観。
豪雪地帯の雪景色は伊達じゃない。
山頂直下の美味しそうな斜面。
スキー、スノーボードを担いで登るバックカントリー目当ての人も多く、後々この斜面には綺麗なシュプールが描かれていました。
11時10分、駐車場から約4時間で守門岳・大岳山頂に到着。快晴無風で絶好のコンディションということで、山頂ではたくさんの人が休憩されてました。
こちらは登ってきた保久礼コースの尾根道。まだまだ続々と登ってきます。
こちらは中津又岳へと至る稜線の雪庇。ここからでもかなり巨大な雪庇が出来上がっているのがわかります。
中津又岳方面に見える山が粟ヶ岳~御神楽岳の山々。まだ登ったことのない山域ですが、この景色を見たらぜひとも登りたくなった。
新潟県内には登りたい山がたくさんあって、こうして登りには来ているけどそのたびに増える一方なので困ります(^_^;)
そしてこちらがお目当ての、”東洋一”と言われる守門岳の大雪庇!
この景色を見たいがために遥々登りにやってきたわけです。
ここからでも十分に巨大な雪庇が出来上がっているのがわかります。厳しい環境下によって雪が吹き流され、それが固まり作り上げられた雪の空中回廊。
見ての通り、床の下は空洞になっているので、誤って雪庇の上に立つと雪が崩れて滑落する危険もあります。
雪庇はその場に立つと全くわからないので、こうやって傍から見てこその景色。
山頂からの越後三山の景色も見事。
勝手に見知らぬ人にモデルになってもらいましたが、人と対比するとそのスケールの大きさがよりわかります。
より間近で守門岳の雪庇を見たいので、もう少し先へ。
山頂は広大な雪原にようになっていますが、ここももちろん雪庇ができていて、あまり左側を歩くと雪が崩れる恐れがあるので油断は禁物。
大岳から下りに差し掛かる絶好ポイントがあったので、ここでのんびりとお昼休憩。最高に贅沢な景色を眺めながらのお昼ごはん、たまらない!
ちなみに目の前の稜線を伝った先の一番高い所が袴岳というピークになります。そこが守門岳の最高地点になりますが、この景色を見たらもう満足してしまったので、今回はここまでにしました。近いように見えるけど、ここから袴岳までは片道1時間以上はかかる道のりです。
のんびり袴岳に登りに行く人を眺めていると、人間がいかに自然に対してちっぽけな存在かというのがわかる。
ほんのひとかけらの雪庇、それと対比しても自然のスケールには遠く及ばない。
東洋一の大雪庇という肩書も、これを見たら何となくわかった気がします。
雪の稜線の先に見えていたのが日光白根山と燧ヶ岳。越後三山に比べると明らかに雪が少なく黒々としています。
流石は豪雪地帯の新潟。思えば昨年12月に日光白根山に登った時も、この上信越方面の雪の付き具合は群を抜いて白く輝いてました。あのときは意識しなかったけども、もしかしたら守門岳も見えていたのかもしれない。
ずっと眺めていたくなるような守門岳の雪の稜線と大雪庇。
遥々登りに来たけども、その見返りとしてはお釣りが来るくらい素晴らしいものでした。
でかい……、デカすぎる!そして、人間が小さすぎる。
改めて見る守門岳の大雪庇の巨大さ。人間と対比するとその大きさが如実にわかります。
ここまで大きな雪庇に成長するのも真冬の厳しい積雪と吹雪という気象条件があってこそ。こうして快晴無風で登れたのは本当に嬉しかった。去年も狙っていたけど、結局天気と休みと体調が合わなくてダメだったからなぁ~、、
小休憩を経て、大岳山頂へと戻る。相変わらずたくさんの人が休憩してました。
この山頂も広いように見えますが、右側半分はほぼ雪庇の上。空中なので、あまり淵の方へ近づくと危険。
登頂時より天気も良くなってきたので、粟ヶ岳・御神楽岳の奥に白い山脈が出現。
これは、紛れもなく飯豊山!この守門岳界隈を凌ぐ、日本屈指の豪雪山域である飯豊山。純白というに相応しい、真っ白な山肌を見せてくれました。
守門岳・大岳山頂に広がる雪原。あまりに広大なために山の上にいることを忘れそうになる。
本当に下山するには名残惜しい景色でした。
天気が良くて風もなく居心地よかったのもありますが、ここまで下山は躊躇われた山も久しぶりな気がする。
ここはぜひともまた訪れたい!
後ろ髪を引かれる思いですが、最後に雪庇を眺めて下山。
中津又岳方面の雪庇。良く見るとトレースが付けられていますが、右の雪庇に近いトレースは間違いなく危険。よくあのルートを行ったもんだ……
そしてこちらはメインディッシュの袴岳へ至る稜線と守門岳が誇る大雪庇。
写真で何度も目にはしてたけども、実際見たらやっぱり迫力が違う。人と対比してみて、さらにその巨大さを実感できました。
12時30分、山頂に1時間以上居座って下山開始。
この時点でもまだまだたくさんの人が登ってくるあたり、冬の守門岳の人気が伺えました。
下山は下山でまた絶景。
この麓の街を見下ろす展望。街との距離が近いのもあってかなりの高度感。ここから夜景が見れたら、さぞ綺麗なんでしょうね。
背負ってきたボードで颯爽と滑るくっしー先生。バックカントリーの模様をGoProで撮影する映像をたまに目にするけど、なるほど、ああやって撮っているんだな、と興味津々で見ておりました。
バックの景色も合わさって最高にかっこよかったですよ、くっしーさん。
下る度に後ろを振り返ってしまう。
本当に守門岳は下山するには惜しいほど、気に入ってしまった山でした。夏の花の時期にも訪れてみたいけど、ぜひとも雪の時期にももう一度来たい。
来た道を戻り、たくさんの登山者によって作られたトレースをなぞって下山。
序盤の林間コースはやっぱり素敵でした。うまく表現できないけども、鬱蒼と茂る樹林帯とはまた違う、ツリーが立つ中をかいくぐっていくあたりに雪国ならではの魅力が感じられました。
常に見えていた越後三山ではあったけども、下山時の展望がいちばん鮮明に見えてました。
左から尾瀬の燧ヶ岳、その横の平坦な山はおそらく平ヶ岳、そして越後三山と、新潟県を代表する山々を見渡せたので大満足。この日の登山はもう文句ひとつなし!
二分駐車場までの下山路。目に見る景色が広いために、トレースがないとここら辺は迷うポイントかもしれません。
橋を越えて登山口へ。最後までスノーシューが手放せない雪山登山でした。
こうして14時50分、二分最終除雪ポイントの駐車場に下山完了。
袴岳に行かなかったので時間的にも余裕かと思いましたが、保久礼小屋から先が長く感じて、割といい時間になっちゃいました。
下山後の温泉は去年、浅草岳に登った帰りにも使った寿和温泉(すわおんせん)へ。守門岳からは少し距離がありますが、他に良さそうなところが見つからなかったのでここにしました。
冬季は露天風呂は閉館しているので内湯のみになりますが、空いていたので快適でした。
こうして温泉にもゆっくり浸かって、今シーズン最後となった冬の雪山登山が終了。
残雪期にも雪遊びには行くかもしれませんが、冬場の登山はいったんこれでおしまい。最後の最後で樹氷に雪庇と素晴らしい雪景色に浸ることができました。
守門岳の大雪庇を見に行く場合、スノーシューやワカンがないとややきついかもしれませんが、山頂からは上信越ならではのスケールの大きい景色が見渡せるので、雪山登山を嗜んでいる人にはぜひともおすすめしたい山です。
東洋一とも言われる守門岳の大雪庇、機会があればぜひ訪れてみてください。
(ランキング参加中)
【日程】
2017年3月12日 快晴
【コースタイム】
7:15 二分冬季駐車場
9:15 保久礼小屋(~9:30)
11:10 守門岳・大岳(~12:30)
14:50 二分冬季駐車場
Copyright © 2017 今日という日を忘れずに All Rights Reserved.