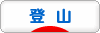(1日目の続き)
2日目はいよいよ剱岳へ。「岩の殿堂」と呼ばれる標高2999mの剱岳、一般的に日本の山の中でも最も危険と言われている山です。
前日に室堂から立山三山を経由して剱沢キャンプ場に幕営。その剱沢キャンプ場から別山尾根を行くルートになります。剱岳登山ルートの中では最も一般的なルートなので、そこまで難しくはないですが、それでも他の山に比べたら危険度は高いです。鎖場の数も半端なく、山頂手前にはあの有名な”カニのタテバイ”、”カニのヨコバイ”という難所が控えています。
初めての剱岳、なかなか緊張感のある山行となりました。
憧れの山、岩の殿堂・剱岳へ―――
「剱岳(つるぎだけ)」、山に登らない人でも名前を知っている人は多いんじゃなかろうか。明治初期まで難攻不落として恐れられた山で、その危険さ・困難さゆえに映画にもなった山です(映画「剱岳・点の記」)。
“世界の果てまでイッテQ”を見ている人なら知ってると思いますが、芸人のイモトがマッターホルン登頂に向けて訓練した山もこの剱岳。
危険な山ですが、一般的な登山者でも登れるルートはもちろん開拓されていて、今回自分が登ったコースも最も一般的な別山尾根ルート。滑落事故が頻繁に起きているので、決して安心して登れる山ではないですが、ある程度山歩きしている方なら十分に登れるかと思います。
アタック拠点からの直線距離は短いですが、アップダウンの連続なのでそれなりの体力は必要です。自分も思っていた以上に疲れました。。。
では、前日に続いて剱沢キャンプ場からのお話。
~~2日目 剱岳登山(別山尾根)~~
9月21日(土)、朝3時半に起床。管理スタッフから「5時過ぎに出発すると渋滞するよ」と言われていたので、なるべく早い時間帯に登りはじめたい。
起床後、朝食を食べて必要な荷物だけをアタックザックに詰め込む。ここのテント場からだと、標準通りに歩けて往復5時間半。途中に水場がないので水は1.5L用意しておきました。
まだ暗い中、ヘッドライトつけて4時半に行動開始。月がいつもより大きく見えて、月明かりがものすごい明るく感じる。こういうことって、都会にいるときはなかなか気づかんよね。気温も思っていたよりも高くて、動きやすい。
月明かりに照らされて、まずはガレ場をひたすら歩く。蛍光マーカーが丁寧すぎるくらいついていたので、暗闇でも迷うことはなかったです。
次第に空も明るくなり、剣山荘手前にある名もなき池から綺麗な朝焼け。陽が出る手前の、この空の淡い感じが一番好き。
テント場から30分ほどで剣山荘に到着。テント場で同時に出発した人はいなかったけど、この小屋からはチラホラアタック開始している人がいました。
この山小屋が山頂までの最後の小屋。ここから先は、簡易トイレ小屋がある以外はもう何もないです。
ここからがいよいよ登り。この先はひたすら岩場だらけで、鎖場も早々に出てきます。
鎖場にはこんな感じで番号が割り振られています。場所によっては登りと下りで専用ルートに分かれることもあるけど、普通に進んでいけば道を間違うことはないと思います。
登るにつれて空がどんどん明るくなってきた。見れば、夕焼けのような綺麗な色!これ、本当に美しい景色でした。山の陰もいい感じ。
ヘッデンも不要になって、行く先も鮮明に。こういうガレ場はマーカーを見逃さないようにだけ注意。所々わかりにくいところもあったけど、たぶん前を歩いている人がいると思うので、その人に着いて行けばいいです。
まず最初のピーク「一服剱」。ここまでは危険個所も特になし。
そして、空が淡い紫色に染まって、ちょうどご来光の時。
5:30、ご来光。今回の旅で何度も眺めてる鹿島槍ヶ岳の背後から太陽の輝きがっ!!
黄金の太陽と青空、そして雲の筋がとても神秘的でした……。しばし見惚れる。
そしてこの一服剱の目の前に立ちはだかるのが、この前剱。本峰はまだこの奥。まだまだ山頂まで時間がかかるので、ご来光を少し拝んだら出発。
前剱までの緩やかな尾根。幸いだったのが登山道が思った以上に空いててくれたことかな。しばらくは前のカップルさんの後をつけていく形になりました。(別に冷かしてるわけじゃないからね、、、)
前剱手前の急な斜面に突入。ここは登っているときは、そんなに大した場所ではないと思ったんだけど、、、
振り返るとなかなかの斜度。後ろにも人がいるので、落石だけ注意ね。実際に、前剱に入る前に「ここから先、浮石注意」の看板があって、所々足場がもろいです。
ここから先は鎖場の連続。ただ、登りではそんなに必要なかったかも。
そういえば、後ろのこの赤い兄ちゃんは早かったなぁ~。あっという間に追い抜いて行った。
斜面が急で、もう空を見上げる感じ。首が疲れて来るぜ。。。
時々立ち止まっては、後ろを振り返ってみる。ご覧のような絶景!目の前が先ほどご来光を眺めた一服剱。左奥の山が前日に登った別山。右奥が剱御前。
所々で紅葉も始まってました。
前剱までの最後の鎖場は確かこの4番鎖場。アングルが良くないけど、右下は崖のようになっていて、こういう横に敷かれた鎖場が割と怖かった。
6時過ぎ、前剱頂上に到着。ここにきて、ようやく見える剱岳山頂。
一服剱からここまでは1時間弱。いよいよここからが本番!
ここから気の抜けない道になってきます。まず前剱のすぐ先にある岩壁。
手すりのないハシゴを渡って、すぐに岩壁を右に回り込んでいくんだけど、これが結構怖い。。鎖に頼りすぎるとバランス崩すかもしれないんで、岩壁に張り付いて慎重にね。今思えば、この5番鎖場が一番怖かったかな、、、。
ちなみに、この部分は下山路は別にあるのですれ違いはないです。そこだけはご安心くだされ。(こんなとこで鉢合わせたらシャレにならん。。)
岩壁の後に垂直に近い下りの鎖場を攻略して(ここ、写真撮り忘れました。ってか余裕なかった、、)、いったん穏やかな尾根へ。
この後も、頻繁に登りと下りのルートがわかれてますが、普通に歩けば下山路に行ってしまうことはないと思います。何よりシーズン中は前を歩いてくれる人がいると思うので、それに着いて行けばOK。
次に待っているのが、平蔵の頭。
垂直の岩場を鎖と足場を頼りに進んでいきます。写真左の鎖場は下山用なので、間違って入らないように注意。
ここも混雑時は渋滞のポイントだそうで。。。この日は、前後にあまり人がいなかったので待ち時間ゼロでしたが、翌日は大変だったみたいです。
登った後にすぐ下り。この下りもなかなか急で、結構怖かった。高度感ありまっせ!
平蔵の頭に関しては行き帰りの道が違うけど、どちらも下りがなかなかのスリルでした。
下ったところが平蔵のコル。ここにきて、ようやく残すは剱岳本峰のみになります。
で、目に飛び込んできたのが、あの有名な、、、
”カニのタテバイ”
別山尾根登山ルートの有名な難所です。ここを越えれば山頂までは危険な道はないので、最後の難関ってやつ。岩壁に人が取りついているのを遠目に見て、「あれかぁ~、、、(汗)」としばらく傍観。
列をなしているけど、まだ渋滞は発生してなくて皆さんスムーズに登られてました。タイミング的には良かったみたい。
とりあえずカニのタテバイの取り付きポイントまで移動。ここ、道が狭くて下山者とのすれ違いも発生するので、譲り合いの精神で!
カニのタテバイ取りつき地点に到着。順番待ちは1人だけでした。下から見ると、本当に垂直の壁。
いよいよカニのタテバイ、スタート。
足場のボルトがしっかりしているので、足の置き場所はそんなに迷うことはないです。下手に鎖を利用するより、岩をつかんだ方がいい場所もあったかな。
足場さえちゃんと確保していれば、そんなに危険ではないけど、なんせ垂直ってのがわかっているんで、登るにつれて高度感が襲ってくる。。。
カニのタテバイ、途中から下を見下ろすとこんな感じ~
幸い、後に続く人がいなかったので、ゆっくり進ませてもらいました。
こういう鎖場とかって、列をなして後から続かれると精神的に焦りそう。。自分も岩場で後ろに人がつかれると、ちょっと嫌です。他の人の落石もあり得るので、できれば空いているときを狙いたいですな。
有名な難所のカニのタテバイですが、実際にはあっさり終わります。思っていたほどでもなかったなぁ……
ただし、その途中にあった、
下山路の難関、”カニのヨコバイ”。こちらの方が見るからに怖そう。。。
実際、カニのタテバイよりも怖かったので、それは後ほど。
山頂までは、もう難所と呼べるものはなし。マークされている印に従って岩場を進んでいきます。
山頂手前、早月尾根との合流地点からの眺め。これまで歩いてきた岩場、さらには立山方面を一望。岩の山なだけあって、開放感は終始抜群!
右下に伸びるのが早月尾根。富山県側の登山ルートで、早月尾根の登山口には、「試練と憧れ」という有名な石碑があります。
試練と憧れ……、まさに剱岳にピッタリのお言葉。一度でいいから見てみたいです。
最後のガレ場。この先に栄光がっ、、!
そして午前7時半、剱岳山頂に立つ!スタートしてきっかり3時間。渋滞もなくて思っていたよりもスムーズに登れました。
記事ではあっさり書いてるけど、なかなかの岩場の連続で体力よりも神経を削られた感じ。疲れました、、、。
けど、やったぜ!!!無事に登頂~~
標高2999m。あと1mで3000mだけど、何となくこの割り切れない感じが剱岳らしくて好き。
山頂からは言うまでもなく360℃の大パノラマ!
登ってきた方面。前日に歩いた別山や立山、さらに目を凝らすと谷間にテント場も見えました。距離的には大したことないんだけど、やっぱり岩場のアップダウンは想像以上に時間取られるんだね。
室堂もバッチリ!正面奥に見えるのが薬師岳。今回の立山・剱岳の旅で、鹿島槍ヶ岳と並んで存在を放っていました。右下の湯気を立てているのが地獄谷。これは次の記事にでも写真載せます。
日本海もすぐ近く。富山の街並みも気持ちいくらい一望できました。
真横にそびえる後立山連峰。右が鹿島槍ヶ岳、左が五竜岳。晴れの日にもう一度縦走してみたい稜線ルート。何年後かに再チャレンジだな。
そして、山頂にきて初めて気づいたのが、遠くに薄っすらと見える富士山。相変わらずの完全なまでの独立峰。他の山を寄せ付けない、目立ちたがり屋めっ!
北アルプスの名峰、槍ヶ岳も存在感では負けてないな。どこにいても良くわかる尖った穂先。北アルプスに登ったら、まずは富士山よりも槍ヶ岳を探してしまう、、、山登りならこの気持ちわかるはず(笑)
こちらは源次郎尾根ルート。手前に見える岩場がⅡ峰かな。世界の果てまでイッテQで芸人のイモトが登ったルートがこちら。ホント、すごいよな。。
対して向こう側に見える鋭利な岩稜が八ッ峰。手前の方たちが登ってきたルートだそうで、曰く「カニのタテバイの鎖なしが何回も続く感じ」とのこと。自分には、もう想像すらつかない世界、、、。すごい人たちですわ、、
最後に剱岳から室堂方面のパノラマ写真を載せておきます。
どんどん人も登ってきたので下山開始。山頂にいたのは15分ほどでした。
下山は下山でまた怖い、、、。というか下りが苦手の自分としては、ここからがある意味正念場。登る時は何でもなかったガレ場も、かなりの高度感。これから写真下に見える岩稜をまた登り下りしていきます。
続々と登ってきました。聞いたら、カニのタテバイ付近で渋滞が始まってたそうな。
あのカニのタテバイ、渋滞するってことは自分が登る時にみんなに見られるってわけで……、いろんな意味で登りづらそう。
で、早速やってきた下山の核心部”カニのヨコバイ”。登りのカニのタテバイと合わせて剱岳の難関とされている場所です。
とにかく高度感が半端ない!下山以上に落石を発生させないように注意ね。
カニのヨコバイはまず鎖場を下って行って、その下に核心部があります。
それがここ、ヨコバイの取りつき地点。
ちょっとわかりづらいけど、黄緑のヘルメットの方がまさに今挑戦している部分。横ばいに取りつくところは、足場を目視できないので鎖につかまって頑張って足を伸ばすしかない。この1歩目が厄介で、他の山行記事でも取り上げられている場所です。
無事に取り付きできたら、すぐにヨコバイが待ってます。ここも垂直に近い岩壁で、足場も不安定なので慎重に。
前の黄色いヘルメットかぶった方がかなり歩き慣れてる感じがしたので、ビビりな自分は、その人がどこに足を置いたのか観察して、その通りに真似っ子。ベテランさんの後ろに着くと楽だわ(笑)
カニのヨコバイをクリアすると、すぐさまハシゴ。別山尾根で唯一のハシゴだったかな。
このハシゴがまた垂直なんだけど、ここら辺りに来ると、この程度のハシゴならどうってことなくなってくる。
前が詰まっているように見えるけど、流れはかなりスムーズで、待ち時間はほぼゼロでした。
この先も鎖場のオンパレード。登りと違って後ろに人も控えているので、オチオチしてらんないぜ!
登りよりはるかに難易度が上がる下山。足場が見つけづらいのが怖い。。
下山途中から行く先を見ると、、、まだまだ越えなきゃいけない壁が控えてる。
手前が平蔵の頭。ピークに人がいるのがわかるかと思います。奥が前剱の門と呼ばれている場所。
岩壁の途中にあったトイレ。よくこんなところに建てたなぁ~、、、というような場所にあります。
下山路の途中にあるので、登りでは見つけづらいかもしれません。
東側の岩壁に出ると日差しも照りつけて、体感温度もみるみる上昇。。。下りの方が神経使うし暑いしで、大変でした。
12番目の鎖場、”平蔵の頭”再び。ここの登りは適度な斜面で、簡単なクライミングをしている感覚で楽しかったです。(家の近くに置いておきたいくらい)
ただ、登ったらすぐに下りなきゃいけなんでね。。。これがまた怖かった。平蔵の頭の下りは少々要注意かと、、、。
いつの間にか後ろに人が全くいなくなっていたので、のんびり下りれたのが良かったです。
前剱。ここまで来ればもう難関箇所は終わったようなもの。見た目ゴツイけど、ここの登り返しは大したことなかったです。
前剱を越えて、最後のピークの一服剱。来るときにご来光を拝んだ場所です。
ここの登り返しが地味に疲れた。。。ここを越えれば後は下り坂なので、最後の頑張りどころです。
鎖とか何もない、こういうガレ場が実は一番歩きづらかったりする。膝にもくるしね、、、かなりゆっくり降りました。
一服剱に登り返して剣山荘を見下ろす。谷を挟んで左の方にテント場も見えたけど、日光浴びてテントの中はサウナ状態になってそう。。置いてきてしまった行動食用のキットカット(抹茶味)がっ!!
一服剱から前剱を振り返る。あの裏側には、うわさ通りのデンジャラスな道が待っていましたとさ。岩の殿堂、そう呼ばれるのもわかるほど岩だらけでした。
あとは緩やかな道を下ってきた道を戻ります。最後までガレ場続きだったので、結構膝にきてました。
剣山荘と前剱。朝来た時は暗くてわからなかったけど、こうしてみるとかなり標高差あるね。剱岳山頂に一番近い山小屋とは言え、ここからでも山頂まで2時間半ほどかかります。途中に水場もないので、水は十分に確保して行った方がいいです。
あとトイレね!渋滞に巻き込まれると、倍近く時間取られるのでしっかり済ませておいた方がいいです。ちなみにこの翌日は、カニのタテバイで2時間待ち、カニのヨコバイで1時間待ちだったそうです。。。侮れないな三連休。。
来た時にも眺めた、池のほとりから鹿島槍ヶ岳と五竜岳。この日も北アルプス全域が快晴だったようで、絶好の登山日和でした。
ガレ場を渡ってテント場へ。「ウポウポ」いう鳴き声が聞こえてたけど、雷鳥だったのかな?しばらく探してみたけど、今回は見つけられなかった。
こうして無事に10時すぎ、テント場に戻ってきました。人気が少なく、静かなテント場。こういう午前中のゆったりした山荘・テント場の雰囲気、すごい好きです。
登り終わって眺める剱岳は、また違った感覚。近いはずなのに、あそこまでの道のりはなかなか険しかった。。時間にしたら往復6時間近くかかりました。渋滞するともっと時間がかかると思うので、できるだけ早めの出発が良いかと思います。
いろいろ危険な場所もありましたが、剱岳登山は無事に終了~!思った以上に疲れたけど、すごい充実感でした!
今回のコースを振り返ってみると、とにかく鎖場のオンパレードで、気の抜けない道が続きました。アップダウンも多くて精神的にも疲れます。
ただ一般ルートなだけあって、要所要所はちゃんと整備されて足場も用意されているので、そこまで進むのが困難なシーンはなかったかな。カニのタテバイ&ヨコバイも時間的にはすぐに終わります。
気を付けるに越したことはないけど、岩場の苦手な自分でも登れたので、ある程度山に登った方なら十分に挑戦できると思います。それと、何度も言うけど、シーズン中は時間を見誤ると渋滞に巻き込まれるので、できる限り早めに登るか週末は避けたほうがいいです。鎖場で立ち止まることになったら、それこそ怖いんでね。。。
さて、無事に剱岳が終わったけど、時刻はまだ10時過ぎ。この後テントをたたんで、場所を再び室堂に移して奥大日岳に登ったのですが……
とりあえず長くなってきたので今日の記事はこの辺で終わり。奥大日岳も、意外や意外に素晴らしい山で、登山ルートで言えば今回の山の中で一番気に入りました。
ひとまず剱岳編、これにて終了~!苦労に見合う達成感、そして山頂には大展望が用意されているので、機会があればぜひ登ってみてください。
2013年9月21日 剱岳山頂より―――
最終回の奥大日編へ続く、、、
【参考コースタイム】
2013年9月21日 晴れ
剱沢キャンプ場(4:30) — 剣山荘(5:00) — 一服剱(5:25) — 前剱(6:15) — カニのタテバイ(7:00) — 剱岳山頂(7:30) — カニのヨコバイ(8:05) — 前剱(8:50) — 剣山荘(9:45) — 剱沢キャンプ場(10:15)