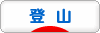今シーズンの雪山登山の1つの締めとして、念願だった鳥取県の伯耆大山(ほうきだいせん)へ遠征登山してきました。
中国地方の最高峰であり、西日本の中でも圧倒的な積雪量を誇る鳥取の大山。標高1729mは日本の山の中では特別高いわけではないけれど、独立峰として凛と佇むその姿が富士山にも似ていることから、「伯耆富士」とも呼ばれている日本の名峰の1つ。
この山は絶対に冬の時期に登りたいと思っていて、雑誌で見たり他の人の山行記録を見ては、ひたすら妄想登山を繰り返していた…。
圧倒的な迫力有する大山の北壁。それを間近で見たくて、、、遥々東京から行ってきましたよ!
今回も絶好の快晴に恵まれ、樹氷に彩られた登山道、雪の豪快な北壁と南壁、雲海に聳える剣ヶ峰のシルエット、想像以上のスケールに満ちていた大山。
今年の冬の総決算とも言える山旅となりました。
中国地方最高峰、雲の上の伯耆大山へ―――
今年は例年になく天気とタイミングに恵まれた雪山シーズン。蔵王の記録の時に、もう欲張りはしない、みたいなこと言ったけど、やっぱりどうしても登っておきたい雪山がまだあってですね、、、
その筆頭が今回の大山。
丹沢の大山じゃないよ。鳥取の大山。東京近郊だと丹沢の大山が圧倒的知名度なので、たまに勘違いされるけど…(´д`;)
西日本では絶大な人気を誇る雪山らしいけど、いかんせん東京からだと遠すぎる……。でも、登っている人が多いから、Twitterとかヤマレコでも色々と情報が入ってきてしまい、いつの間にか登りたい願望が物凄い強くなっていた山。
正直なところ、今シーズンは半ば諦めかけていて、3月の最初の週に行けなければ来年に回そうと思ってました。東京から米子までの高速バスを予約したのが2月の半ばだったかな…?
休みも限られているので、予備日もあまり取れない。でもせっかく行くなら絶対に快晴じゃなきゃ嫌だ!ってことで、少しでも天気が悪そうなら即キャンセルするつもりだったけど、、、
今回もまた天気が味方してくれましたよ!!樹氷に雲海、そして自身初となるブロッケン現象まで見れて、まさに最高のコンディションで山登りをすることができました。
屋久島以来の西日本の山に、いざ出陣!!!
~~ 2015年3月8日 冬の伯耆大山 ~~
登山のスタートは大山の麓のロッジから。ここに至るまでの経緯は機会があれば別で書くけど、前日は山陰観光しておりました。
麓からスタートなので、睡眠も十分に取れて体調も万全!泊まったところがスキー場のロッジで、久しぶりに登山前にまともな朝食頂いちゃいました。
ただ朝7時に意気揚々とロッジを出たのたけど……朝の天気は見るに堪えないガスっぷり、、、orz
予報では晴れマークが出てたので(前日の天気は裏切られたけど…)、何とかそれを信じて登山口へ向かう。大山の麓には「だいせんホワイトリゾート」というスキー場があるので、ペンションがたくさん立ち並んでます。
そしてその中で、登山者としては「おっ!?!?」となるポイントが…
こちら、登山口のすぐ近くにある、「モンベル大山店」。こんな山の麓に店を構えるあたりが、大山の人気を象徴している。春夏秋冬、どのシーズンでも魅力を備えている大山。年間通じて登山者がたくさんやってくるあたりは、八ヶ岳に通じるものがある。
モンベルのテラスが大山の絶好のビュースポットにもなっているだけど……
今は山の影1つ見えやしない…。「これ、本当に晴れんのか??」ってこの時は悲壮感漂ってたけど、、
晴れるんです!!!
駐車場わきのこちらが登山道入り口。週末なのでトレースバッチリ。先行者もたくさんおりました。
見た感じここの入口はわかりづらいので、平日のノートレースの時は見落とす可能性あるかも。
登山届に関しては、少し先にボックスが用意されているけど、大山の場合はWebサイトから提出できるので事前に済ませておけます。
序盤はただの樹林帯。今歩いているのは夏山登山道と言って、冬でも標準コースになっています。というか、他はバリエーションルートになっているので、ルートの選択肢としては基本的にここ一択。団体さんも多くて、早い時間でもそこそこ人がいました。
スタートして30分くらい経った頃かな?
ずっと晴れを祈りながら登っていたら、何か空が明るくなってきてさ
何か青空見えてきたっ!
そしてそれ以上に興奮したのが、辺り一面に広がっていた美しすぎる樹氷の世界。
本当に突然、樹氷の景色へと変わった。何も面白味のない樹林帯から一転しての樹氷のトンネル!
カメラの火が一気に付いた瞬間でもある。
こんな樹氷群にありつけるとは思ってなかった。
…というのも、この日は気温が高くて半袖でも登れるレベル。前日から今朝の悪天がもたらしたんだろうね。そう考えたら、今朝のガスっぷりにも感謝するしかない。
この天気回復があっという間で、サーっと舞台の幕が変わるかのように青空一色になった。
青空と樹氷、雲の移り変わり、全てが幻想的なシーンとして目に映る。
西日本の富士山とも呼ばれている大山。登山口から山頂までは標高差1000mほどだけど、独立峰であるがゆえに富士山と同じく登山道が山頂に向けてストレートに伸びている。無駄なアップダウンが一切ない分、急登が続きます。
アイゼンは早々に着けた方がいいです。ピッケルは使わなかったけど、斜面がきついので12本アイゼンは必須。
ただの樹林帯が続いてたら、かなりきつい道だったろうけど、周りは樹氷一色。
青空に映える樹氷が綺麗で、疲れ感じず冬景色の美しさに見惚れておりました。これだから、雪山はやめられないぜ!
ある程度登ると、途中に開ける場所が出てきます。
自分の中では、待ちに待ったシーン。
樹氷の奥に見えてきた大山の山頂。そして今見えている岩壁が、念願でもあった大山の北壁。1つの山といて括るにはあまりに大きすぎる、大岩壁。
これが見たくて、遥々東京からきたんです!!まだスタートして1時間ほどしか経ってないけど、早くもピークを迎えて泣きそうです(;;)
森林限界を迎えるまではひたすら樹氷群。標高が上がるスピードが速いので、視界が開けるのも早いです。
振り返ると、ちょうど雲の位置に並んだ。標高はまだ1500mにもなっていないポイント。
この日はやたらと雲の位置が低くて、、、こうなってくると、雲海を期待せずにはいられなくなる。
辺りに広がっていた樹氷もいつの間にか消えていき、そうなると大山の北壁が一面に現れる。
北アルプスの岩稜帯を思わせるこの風格、見事としか言いようがない。
朝のうちは少し風が強かったけど、登る分には問題なし!
むしろ、ガスを取っ払ってくれて、ありがとうございましたm(__)m
北壁を挟んで向かい側、三鈷峰方面を覆う雲。この雲が次第に取れていく様子に、また神々しさを感じる。
これはこれで見惚れてしまう光景でした。
はっきりと見えてる山頂。すでに下りてくる人もいて、話を聞いてみたら、山頂のほうが風が弱いとか。地元の人っぽい方からも「今シーズン一番のコンディションじゃないの」ってお墨付き頂きました。
真っ白く輝いて、眩しすぎる冬の伯耆大山。
西日本屈指の豪雪の山は北アルプスや東北と遜色ない雪のつき方で、本来なら途中にあるはずの6合目避難小屋も完全に埋まって見つけられませんでした。
BCも有名らしく、いくつものシュプール描かれてるね。
相変わらず急登は続く…。この日は雪が締まっていてアイゼンも効いたから難なく登れたけど、降雪後は結構キツいかもしれない。。こんな急斜面でラッセルとか、やってみたいようなやってみたくないような…。
そして、振り返ってみれば早くも雲海!写真見てもらうとわかるけど、大山周辺だけがぽっかり穴が開いたように晴れていて、麓のスキー場も見えました。
本来なら正面は日本海なんだけど、それはまた後ほど。
そしてこの時、前を歩いているあつしがあることに気付いた。
それが、こちら↓↓
うぉ!?!?
これは、まさか……。ブロッケン現象ってやつではないですか!?これ、ブロッケンですよね?
登山5年目にしてついに見れました、ブロッケン現象!!雨上がりの日なんかによく見れるって言うけど、これまで一度も見たことがなく、、、自分の中では神話化されつつある自然現象だったけど、まさか鳥取で見れるとは思ってなかった(笑)
樹氷に続いていいもん見れました。前日の出雲大社での御縁祈願が効いてたと思うことにする。
山頂はもう見えているけど、まだ1時間ほどかかる距離。時間は8時半ごろで、確かこの辺りが一番風が強かった。
それでも、1ヶ月前の宝永山に比べたらそよ風並だったし、もう3月で気温も高いので寒さは全然感じず。オーバーグローブも必要なかったです。
このルートで6合目の避難小屋が埋まってしまうとポイントらしいポイントがないので、ペースが早いのか遅いのかがわからなかったけど、樹林帯を過ぎてからは体感的にはあっという間。
スタート7時って、山登りでは決して早くはないけど、このルートは往復6時間あれば登れてしまうので、9時以降に登りはじめる人もたくさん。自分たちはむしろ先行隊だったかな。下山時の混雑っぷりを考えたら、まだまだ空いていた方でした。
登ってくると、また北壁も違って見える。優雅な曲線美。薬師岳や仙丈ヶ岳のカールを思わせる滑らかさがありました。
9時、標高1600m地点に到達。雲よりだいぶ上にきました。この標高でこれほどの雲海が見れるのは貴重。
標高1600mってさ、、、普通なら雲海は期待できない標高だと思う。
試しに標高1600mで検索してみたら、、、「標高1600メートルで初代ウェルター級王座決定戦 」ってキックボクシングのサイトがヒットしたんだけど……、今はどうでもいいか。
K-1、PRIDE、大好きっ子だったので、格闘技の記事は見逃せないけど (¬д¬。)ボソッ
ここまで来ると残り標高100mは緩やか。稜線を伝って山頂を目指します。
ずっと見上げていた北壁も見下ろす感じになってくる。独立峰とは思えない大岩壁。大山のスケールの大きさを感じずにはいられない。
気温は高いけど、山頂付近はまだまだ雪と氷だけの世界。雪のモニュメント、シュカブラ、雪庇もかなり育ってました。
下から吹きつける風が雪煙を舞い上げて、さながら雪のシャワー。
すれ違った人が言ってた通り、下の方が風が強くて、山頂に近づくほど風は収まる。
雲海をバックにボード担いだ兄ちゃん2人。カッコよく絵になっていたので撮らせてもらいました。
こんな感じでスキーやボードを担いで登っている人も結構いました。
この人たち見て思ったけど、今年はついにゲレンデで滑りに行くことは無さそうです。上州武尊山の下山時に1本滑ったのが最初で最後だったか…。確か去年の冬の終わりに「来年は雪山登山とボードをもう少しバランスよく行きたい」なんて言ってた気がするけど、今年は余計に雪山に比重が傾いたシーズンでしたとさ。
でも、やっぱり今は登る方が楽しさを感じるからこれでいいと思ってる。来年も雪山8割、ボード2割で多少滑れればいいや程度で、ここで宣言しておく(笑)
山頂は近いけど、見るもの全てが絶景なので、なかなか前に進まない。
自分↑(笑)
土下座しているわけでも祈っているわけでもなく、シュカブラが綺麗だったので、カメラ構えてみたけど…
全然よく撮れてない…。カメラのセンスもう少しあげたいわ。。
そういえば、前回の大霧山の記事でポンコツカメラを卒業するって言ったけど、今回新しいカメラに変えました。少しは写真もマシになったはず!!(気づいてくれた方、ありがとうございますmm)
ついに一眼レフにしようかと思ったけど、やっぱり重いのは嫌なので2台目のミラーレスです。
登山ではぶっつけ本番で、しかも念願の大山で新しいカメラ投入したけど、まぁまぁ綺麗に撮れてると(自分では)思う。
前日の観光で使い慣らしておいた甲斐があったぜ。
ちなみに使い慣らしたと言っても、設定を少し変えたくらいで、後はオート機能に任せてます(^^;
仲間からも宝の持ち腐れと言われているので、少しカメラは勉強したいかな。。写真のクオリティーを2割上げるのが、今年のこのブログの1つの目標。
9時20分、頂上避難小屋に到着。ここから山頂は目と鼻の先。
1Fは完全に埋まってるけど、見た感じではかなり大きな避難小屋です。
入口はこんな感じで穴が掘られてました。中覗いてみたけど30人以上は楽に泊まれるんじゃないかってくら広かったです。
この日は日差しが届かない分、小屋の中のほうが寒いくらいでした。
すぐ目の前の丘が伯耆大山・弥山の山頂。今は空いているので、サクッと登ってしまうことに。
あそこに立つと、本日一番の絶景が待っていたんだな、これが…
ドンっとな!
9時半。弥山山頂到着!これが山頂からの景色。
雲海が広がっているのは承知してたけど、ここまでの絶景が待っているとは思わなかった……
まさに雲の上に聳える雪山。
あれ?少し先が山頂かな?って思ったけど、地図上のピークはここで良いみたいです。
あっという間に登ってきた感じがするけど、何ともまぁ見事な雪の伯耆大山。雲の上に聳えるその風格は2000mに満たない山とは到底思えない。
奥にある尖がったピークが剣ヶ峰。一応縦走禁止区域になってますが、この日はコンディションも良くて、結構たくさんの人が剣ヶ峰へ向かってました。積雪時だからこそアタック可能な道なのかね。
この写真、良く見たらちょうどピークに人が立ってますね。撮ってるときは気づかなかった…
雲に浮かぶあたが、(ベタだけど)ラピュタ城を彷彿させる。
せっかくなので先へ。こんな感じの狭い尾根を伝っていきます。トレースバッチリなので、ここら辺はまだ滑落する心配なし。
横を見れば相変わらずの雲海。雲も朝に比べたらだいぶ取れてきてます。
これぞ雲の上のスノーハイク!たまらんです。
1つ先のピークを越えたところから、再び剣ヶ峰。あそこまでの縦走路もひたすらやせ尾根が続いていて、滑落事故も結構起きているんだとか。
先行く人のほとんどはハーネス、ザイル、ヘルメットのガチ装備でした。自分たちはあいにくピッケル・アイゼンしか持ち合わせていなかったし、事前の登山届にも剣ヶ峰まで行くことを書かなかったので、剣ヶ峰までは行くつもりは毛頭なし。
この山脈を眺めるだけでも十分素晴らしい!雪山の陰影ってどうしてこうも綺麗なんだろうかね。遠くまで続く雲海、これが標高1700mの世界とはとてもじゃないけど思えない。奥多摩で言ったら鷹ノ巣山よりも低い位置だからね。
雲海にぽっかり開いた穴1つにも自然の力を感じる。
この稜線に立って初めて目にした南壁。大山はこの南壁と北壁に挟まれた痩せ尾根にピークが点在する尖鋭の山。
最初にも書いたけど、剣ヶ峰以上に、この岩壁が見たくて遥々東京からやってきました。無事に見れて、感無量でございます!
しかもこの雲海というご褒美つき。
南壁に見惚れて、ふと北壁側に目をやると、下から登山者が登ってきました。
このルートは弥山尾根西稜。北壁を目の前にしながら登るバリエーションルートで、夏山登山道からも目を凝らすとこのルートで登っている人たちが見えました。
貫録十分で颯爽と登場するあたりがカッコよかったです。
ダイナミックな北壁と剣ヶ峰。ここまで迫力ある風格を感じられた雪山は、初めてかもしれない。簡単に登れて、こんな危険と隣り合わせの風景に出会えていいのかってくらい。
剣ヶ峰と名のつくところは色々あるけど、いずれも剣のように尖ったシルエットが特徴的なので、見ているだけで満足させられる。
上州武尊の剣ヶ峰もしかり。剣ヶ峰ハンターとして、日本中の剣ヶ峰を回ってみるのも面白いかもしれないな(やらないけど…)。
写真見てもらうとわかるけど、この時山頂目指す人とがみんな手前のピークで停滞していて「何があったんだろう…?」って思ったな。
それならば、私たちが行こう…
って感じで、これまた颯爽と先ほどの西稜を登ってきた2人が歩いて行きました。おそらく年配のご夫婦。
恐れ入ります、、、どうぞお通りくださいmm
って具合にササっと道を譲る渡しました。
せっかくなのでパノラマ写真も撮ってみる。山に登って雲海を見ることはあるけど、これだけ果てしなく敷かれた雲海を見たのは久しぶりだな。雪山ではなおさら。
こちらは三鈷峰。あの山も西壁と東壁から成る切り立ったピーク。
右に見える山小屋は「ユートピア避難小屋」。避難小屋に横文字とは初めて聞いた(笑)
可愛い名前がついているけど、なんちゅ~危険な場所に建っているだか……。大山は奥が深い。
相変わらず手前のピークで停滞している先行隊。どうしたんだろうかね…。心配になるくらい誰も先へ進んでませんでした。
確かにこの時間帯は少し風が出始めてたし、弱まってるのを待ってるんだろうな~、、なんて素人分析してた。
こちらはもうちょい先までお散歩。ここら辺はすれ違いも困難なほどのやせ尾根なので、混雑時は進まない方が無難。
写真左が北壁、右が南壁。
その高度感といったら半端なかった……
うひょ~!!これは落ちたらひとたまりもありませんな…。
はるか下に不気味にガスが滞留しているのがまたいやらしい。
それでも一時強かった風も、この時間帯になるとほぼ無風で、トレースもバッチリついていたので弱高所恐怖症でもそれほど怖さはなく、北壁と南壁まで見下ろせる場所まで行けました。
剣ヶ峰アタックへ向かう登山者たち。こういう危険な道を最初に切り開いてトレースつける人ってのは、やっぱり相当すごい岳人なんだろうなと思う。
何度写真に収めたかわからないけど、剣ヶ峰と雲海。
中国地方最高峰の偉大さは十分すぎるほど感じられた。東京からは遠いけど、西日本の人からするとインターからのアクセスもいいし、米子駅からバスも出ているので、かなり身近な山なのかもしれない。近くに雪山が少ない分、この山に人気が集中するのも十分わかる。
もし近くにこの山があったら、1シーズンに何度登りに来てたんだろう…。それくらい気に入ってしまいました。
ちなみにこの伯耆大山、日本百名山に選ばれているのはもちろんだけど、実は日本四名山という日本を代表する4つの山の一角でもあったりする。富士山、立山、御嶽山、そして大山。大山以外は標高3000mを越える山だけど、その標高差をまるで感じさせない偉大な名峰でした。
日本四名山、意識してなかったけどこれで一通り登頂完了。
お目当ての大岩壁、上から見下ろした時の高度感といったら半端なかったけど、荒々しさと同時に壮麗さも感じられました。
もうね、、、十分報われたよ!遠くまで来て、本当に良かった…
正直なところ、昔ほど貪欲に山に行こうとする気はなくなってきたけど、晴れを信じて登りに行くのも必要なんだなと改めて思った。最近は天気予報に敏感すぎると自分でも思ってるからね。
もう少し、気楽に行きたい。
弥山まで引き返すと、登ってくる人も増え始め、徐々に賑やかになってきてました。
相変わらず周りは雲海。町並みが見えないのは少し残念ではあったけど、、、
日本海方面は晴れてきてくれて、弓ヶ浜の湾曲の海岸線が見渡せました。
雲の海とリアルな海、同時に見渡せるって早々ないシーンでしょ。
狭いピークも定員オーバー気味(^^;
早めに登っておいて良かったかも。この弧を描く稜線が、また稀に見る様相で見入ってしまう。
もう何度目かのパノラマ撮影。1つの山で括るには広大すぎる大山。
後ろ髪を引かれる思いというのはまさにこのことで、できることなら帰りたくはなかった。この場から夕日に照らされる大山も見てみたいと思ったよ…。
それでも(考えたくはないけど)、明日から仕事。今日中には東京に帰らないといけないので、足を麓へ向ける。
遠くて簡単に来れる場所では決してないけど、降りる間際に絶対にまた登りに来ることがあるだろうと思った。山で危険を犯してまで登ろうとは思わないけど、この山に登ってまた1つ目標ができたし、雪山登山でももう1歩ステップアップしても良いかと思った。
また来年の「行きたい雪山リスト」が賑やかに増えそうだけど、次に繋がる山旅となったのは収穫。今シーズンで積雪時に登りたい雪山はある程度登ったつもりでいたけど、、、いやいや、まだまだ全然物足りないな(笑)
来年の雪山シーズンもどうぞよろしくお願いしますmm
頂上避難小屋で少し早目のお昼休憩。山頂を見ると、すごい数の登山客で改めて人気の高さを感じられた。
下手したら、八ヶ岳より多いんじゃないか、ここ!?
下に目を向けると、登るときには気づかなかった巨大な雪庇。こういう風景1つ取って見ても、自然の力の偉大さってのを感じずにはいられない。
登山ってやっぱりいいもんよ。山を初めて、改めて日本の奥深さってのも感じたし、たとえ名前は知らなくてもその時々で色んな人と話せたり交流できたりもするからね。
11時前、予定よりもだいぶ早いけど混んできたので下山開始。名残惜しさは十分にあるけど、また来ればいいや。海外ってわけでもないし、バス2本乗りつけば来れる山だってわかったからね。
下山は下山で急斜面を下りないといけないので要注意。登ってきたとき以上に神経使いました。
もうじき正午を迎える時刻だけど、まだまだ登りに来る人はたくさん。
自分がこれまで登った雪山の中では、一番混雑してました。八ヶ岳や谷川岳よりも人多い。
でも、考えようによっては当然なのかもしれない。みんなアイゼンもピッケルも携帯してたけど、この付近でアイゼン・ピッケルが必要になる山ってそれほど多くはないはず。圧倒的な積雪量を誇る大山に人気が集中するのは、仕方のないことなのかもね。
すれ違いを待っている間に、ボーっと日本海を眺める。登っているときには雲海で隠れていた海も、この時間にはすっかり晴れ渡って一望。
右に見える低山は孝霊山。標高751mとかなり低いけど、大山側火山でもあり鳥取県の中では名峰の1つ。
下りている際に、何度も振り返ってしまう北壁。
登ってきたときとは太陽の位置も違うので、北壁の陰影が違ってまた魅了されてしまう。
これから登る人が羨ましくさえ思える。できることなら避難小屋泊でもして、しばらくこの山と向かい合っていたかった。
樹林帯に戻る前に見納め。絶対にまた来ます!
伯耆大山、北壁全景―――
樹林帯に入って早々、美犬との遭遇。真っ白いモフモフな毛並みが雪山に良く似合ってました。
気温が高いので、樹氷が溶け落ちて足元には雪の結晶たくさん。
上からバラバラ落ちて、頭に当たると痛てぇ…
朝見れた樹氷もこの日限りのものなんだろうね。
白く輝く樹氷。樹が白い花びらを纏っているようにさえ見えた。これも1つの冬の絶景。
登っているときには気づかなかった登山口脇に佇む神社、大山寺阿弥陀堂に寄り道。
重要文化財の1つでもある、由緒ある神社。
晴れてくれたことへひたすら感謝。遠くから遥々来た甲斐ありました。
本当にありがとうございましたm(__)m
御参りも終えて、今回の山登りも無事終了。
登山口を過ぎ、朝来た道を戻る。右奥の建物が最初に紹介したモンベル大山店。
朝はこの橋から山を見上げてもガスに包まれてたけど…
下山後はバッチリ大山の真っ白な山脈見渡せました。
この麓からの眺めがまた素晴らしくて、日本とは思えない雪山の風景。アルプスさえ凌ぐ凛々しさがありました。行ったことないけど、ヨーロッパの本場アルプスさえ彷彿させる壮観な景色でした。(ヨーロッパなんて行ったことないけど…)
左の三鈷峰もいつか登ってみたい。
下山後の温泉は鳥取で有名な皆生温泉に行こうかと思ってたけど、思ったより時間あるので麓で済ませることに。
モンベルの近くにあった豪円湯院。
「大山の頂上に1番近い温泉!」
こう言われちゃ、入るしかないな!
日帰り入浴600円とお安く、館内がめちゃくちゃ綺麗で山の麓の入浴施設とは思えないクオリティー。露天も広くて空いていたのでかなり快適でした。
唯一残念だったのは、男湯の露天からだと樹が邪魔で大山があんまり見えなかった。位置的におそらく女湯からなら見えると思います。
でも、総合的にはすごいおススメできる温泉です。
風呂上りに大山の霊水も頂く。よくわからないけど、還元力なるものが最大級の水らしい。
風呂でさっぱりして、旅館街を散策。海へ向かって伸びる道、旅館街の落ち着いた雰囲気が風情あって好きでした。
こちらが大山寺バスターミナル。売店の類はないけど、自販機とトイレ、更衣室、ロッカーなどが完備。スキー場も併設されているので、この手の設備は充実してました。
せっかく遠くまで来たので、普段は買わない登山バッチを購入。屋久島、飯豊山に続いて3つ目かな。
この雪山タイプの登山バッチは「チロル」というロッジで販売してました。ターミナルで教えてもらったので、登山バッチ買う場合は問い合わせてみてください。この時期は、そもそも登山バッチを売っている店が限られています。
それと地酒もな(笑)
パッケージが気に入って即購入。ただ昨年10月の南アルプス縦走で買った赤石岳もまだ開けてないし、だいせんを呑むのもいつになることやら…
14時50分、米子駅行きのバスに乗車。名残惜しさ半端ないけど、十分満足させてもらったので帰ります。
バスの車窓から伯耆大山。遠目から見て、初めて富士と呼ばれている所以が改めてわかりました。
下から見上げる大山とはまるで違う姿。
(※大山を眺めたいなら、バスは向かって左側の席に座ることをお勧めします)
16時前、米子駅着。今回は米子市内は観光しなかったけど、この駅には色々とお世話になりました。
駅構内のハートインっていうコンビニは、思ったよりも品揃え豊富で、登山前の買い出しにも利用できるかと思います。このコンビニを当てにせず、少し離れたローソンまで買い出しに行こうとしたのは前日の出来事。(今回のターニングポイントにもなったその話は、機会があれば観光編として別で書きます)
旅のドラマは米子駅から――
この旅はこれでおしまいだけど、始まりはまさにこの米子駅からだったな。
鳥取県って言うと、スタバが最後まで進出しなかったり、セブンイレブンが未だにない県だったりするけど、大山があれば十分でしょ!もっと誇らしげに構えていいと思う。
十分楽しませてもらいました。
改めて帰りの電車から伯耆大山。富士の山容そっくりな出で立ちでお見送りしてくれました。
街中からもすぐ近くに見えるし、米子総出で観光地として推しているあたり、この地域に色濃く根付いている山なんだろうね。
期待は当然していたけど、そこで待っていた雪の世界は想像をはるかにしのぐものでした。
今回の山陰の旅は他にもあるけど、山の記録としてはいったんこれでおしまい。
だいぶ長く語ってしまったけど、序盤の樹氷からのブロッケン現象、そして雲海に映える剣ヶ峰と、見どころ満載の大山の山旅となりました。
スタート早々の樹氷群は言わずもがな。その背後に見えた大山北壁の迫力といったら言葉では言い表せないほど。念願の北壁も間近で見れたし、遥々遠征した甲斐があったってもんです。
そして山頂に到達してから目にした、雲に浮かぶ大山の稜線。標高1700mを感じさせないその堂々ったる風格は、流石は中国地方最高峰!
人気が出るのもよくわかったし、1回の山旅ではその魅力を全て感じ取ることは到底できないというのがよくわかった。
剣ヶ峰はもちろん、その奥の槍ヶ峰。さらには三鈷峰や北壁へ真っ向から仕掛ける西陵ルートなど、大山はまだまだ奥が深い。
登り終わって間もないけど、早くも来年に向けたプランニングをしてしまう自分がおりました。
それだけ魅了された、鳥取の伯耆大山。下手したら来年もまた登りに行ってるかもしれない。
今年の雪山シーズンの1つの締めとして、十分すぎる感動を得られた山旅でした。
もう季節は厳冬期を終えて3月に入り、春の花の季節を迎えつつあるけど、もう少し雪遊びを続けてもいいかなとも思った。
次の山の予定は何も決まってないけど、残雪登山と春の花の旅、両方楽しんで行けたらと思います。
長くなったけど、今回も読んで頂きありがとうございましたm(__)m
念願の大山北壁より―――
おしまい。
↓↓ブログランキング参加中↓↓
今回も読んで頂きありがとうございました。
【日程】
2015年3月8日 快晴
【コースタイム】
大山寺(7:00) — 夏山登山口(7:10) — 頂上避難小屋(9:20) — 大山山頂・弥山(9:30) — 夏山登山口(12:20)