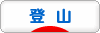北アルプスのじいちゃん、標高2670mの爺ヶ岳へ行ってきました。
4月中旬に毎年開通する立山黒部アルペンライン。山に登らずとも、観光名所の雪の大谷がニュースにもなるので知っている人も多いはず。その開通に合わせて扇沢までの林道も開き、爺ヶ岳登山口までのアクセスも可能になります。
ただ、それでも4月中はまだ登山道は雪の中。通常ルートの柏原新道は通れないので、冬期ルートとして臨時で用意されている南尾根ルートで登ることになります。
冬期ルートとしては東尾根よりは格段に楽な南尾根ですが、それでも標準ルートではないバリエーションルート。乗鞍岳よりは簡単には登らせてくれないだろうなと不安1割、期待9割で挑んでやりましたぜ!
暴風予報が発令で、登山口に着いた時には不安2割くらいに増していたけど、そこで出会えた景色は素晴らしいものがありました。毎度のことながら、北アルプスの偉大さを感じずにはいられなかった…
そんなわけで、乗鞍岳に続く2015年北アルプス山行第2弾!
北アルプス後立山連峰の爺ヶ岳へ―――
爺ヶ岳に移る前に……
ここ最近の天気は何なんですかね?
晴れるのはいいけど気温が高すぎじゃないですか。もう夏だよ、夏。今日なんて半袖短パンで十分だったし、モーニングのホットコーヒーも美味しく飲めやしない…
通勤電車の中も蒸し風呂状態で正直きつい。。。雪山に逃げたい。というか、こんな日々が続いたら山の雪もあっという間に融けちまうよ…
そんな不満が募る日々だったので、前々から計画していた爺ヶ岳はタイミング的にはちょうど良かった。4月は他にも山に行ってたけど、とりあえず記憶が新しいうちに爺ヶ岳を先に書いておきます。
~~ 2015年4月18日 爺ヶ岳南尾根 ~~
毎年4月中旬に開通を迎える立山黒部アルペンライン。この開通を迎えると、いよいよ北アルプスにも春が来たんだなと思うようになったのは、3年くらい前からか。
扇沢。室堂へのアルペンライン開通と同時に林道の通行止めも解除されてこれるようになる登山拠点。
ここに初めて来たのは3年前の同じく初めて爺ヶ岳に登りに来たとき。その時は鹿島槍ヶ岳~五竜岳まで縦走したけど、正直天気があまり良くなかったことだけ覚えていて、旅の記憶は薄れつつある。
今回は、その時見れなかった景色を求めて再訪した旅でもありました。
スタートは扇沢少し手前の爺ヶ岳登山口前駐車場。10台ほどしか停められないけど、早朝4時半に到着した時はまだ空きがありました。
軽く仮眠して朝6時半のスタートを迎える頃には青空一色!目の前には北アルプスの輝かしい山壁。都内の蒸し暑さを忘れさせてくれるよ。
3年ぶりの爺ヶ岳登山口。たった3年かもしれないけど、その間によう山に行ったわ。北アルプスの地理も当時と比べたらだいぶわかるようになった(はず)。
登山口のポストに登山届を提出して出発。今回は男5人。個々でそれなりに雪山も登っているけど、この5人で一緒に登るのは初めてか。
あつし、たくみ、まさき、すすむ、どうぞよろしく。
南尾根ルートで登る場合も、しばらくは柏原新道を歩くことになります。
とは言っても、道は雪で隠れていたりもするので、決して歩きやすくはない。
朝は雪が硬かったのでアイゼンつけたくもなるんだけど、、、
雪がとけているところも結構あるので、アイゼンつけるにつけれない。
今年は雪解けが早いそうなので、本来ならもう少し雪が残っているはず。道が明瞭でわかりやすいのはありがたいんだけどね。
この後も雪があったりなかったりの繰り返し。
登りはそこまで急じゃないけど、やたら暑い…。登っている間は半袖で十分ってことで気合入れて肌を露わにした矢先、枝にスパッと腕をやられて早々に切り傷を食らったのは、情けなかったな…。
なんで雪が残っているのかわからないくらいの気温。この日だけでも相当雪は融けたはず。
日焼け止めが汗で流れていく。。(でも、めんどくさいから塗りなおすことはしない)
7時10分、八ッ見ベンチに到着。思っていたよりも早く着いた。
ここから見る針ノ木岳に癒された。あちらは未踏の山。
個人的には隣の蓮華岳に興味があるから、近いうちに合わせて登りに行きたい。
下を見ると土石流が凍って固まったように雪崩れた雪渓が目に入った。こういう些細なワンシーンでさえ、自然の力強さ、恐ろしさを感じる…。
八ッ見ベンチの先が南尾根への取りつき地点。わかりやすく看板が設置されているので、取りつきポイントで迷うことはないです。
5月までの積雪時に用意されている冬山限定ルート南尾根へ。
林間コースを縫って登っていく。たまに赤テープもあったし、幸いトレースも薄らついていたのでルートファイティングを駆使して登るようなことはなかったです。
ただ、整備されている道でもないので、枝や倒木が時折邪魔。序盤の枝による攻撃を受けて、枝の攻撃力がなかなかのものだと知っているので侮れない。
もともと今回は1泊2日で爺ヶ岳~鹿島槍ヶ岳の予定だったんだけど、暴風予報もあったし色々な都合で日帰り爺ヶ岳に変更。
荷物も軽いし時間に余裕があるので、ゆっくりペースで登る。
写真の技術は全然向上しないけど、仲間の隠し撮りの腕はそこそこ上がった気がする。自然体が好きなんよ。
樹の合間から先を行く仲間を激写。バリエーションルートなだけに、こういう短い距離も迂回していかなきゃならないから、うかうかしていると距離はなされる。
と言いつつも、色々と自然に目を向けてゆっくり鑑賞に浸る。これがサクランボじゃないってのは、いくら花や植物に詳しくない自分でもわかるけど……
これは何の実ですか?
登って行くにつれて、展望も良くなる。柏原新道よりも標高を上げるペースが速いので、展望も早々に開けてきます。
南尾根いいじゃない。思っていたよりも道が明瞭なので、全然迷う心配なし。
という言葉を、最後尾にいて仲間について行くだけの自分が言うなって話か…( ̄▽ ̄)
滑らかで穏やかな稜線。ヤマレコとかを見ていると、この手のメローな稜線を「美味しそう」って表現する人がいるけど、何となくわかる気がする。
うーむ、、何度も振り返ってしまうのが針ノ木岳。扇沢に来るとどうしても立山室堂へ目指しがちだけど、爺ヶ岳と同じく針ノ木岳も扇沢拠点で登れる山としては魅了されるな。
日本三大雪渓の1つ、針ノ木雪渓も良く見える。
眼下には扇沢も見えました。見ての通り、4月中旬のGW前なのに駐車場は大繁盛。
北アルプス南部の登山拠点が上高地なら、北部はこの扇沢だと思う。
景色に見惚れつつ、所々急斜面なので頑張って登る。
上から見るとなかなかの急斜面。滑って落ちるとたぶん一気に沢まで連れていかれるので、お気を付けください。
早朝なのでまだ雪はツルツルです。
ジャンクションピークへ向かう雪の尾根道へ出た。
ここでようやくアイゼン装着。ここから先、ジャンクションピークに出るまでは結構な斜面を登ることになります。
アタック開始。所によっては登るというより這い上がる感じ。
距離的にはそんなになさそうだけど、なかなかの標高差。
先は長そうだ……
融雪が早くて、時々踏み抜くこともあるのでご注意くだされ。残雪期は日単位でルートが変化する。
アイゼンかましてひたすら登る。ここは見た目以上に長く感じました。
疲れるけど標高は一気に稼げるので、無駄なアップダウンがないだけまし。
だいぶ登ってきた。上から見るとここもなかなかの急斜面。
そして、相変わらずバックの針ノ木岳が美しい。
ジャンクションピークまであと少し……
ここら辺まで来ると、バックに北アルプス南部の山も見えてくる。特に目立っていたのはやっぱり槍ヶ岳。北アルプスの角は流石の存在感。
9時20分。ジャンクションピークに到着。ここに来てようやく目指す爺ヶ岳を見ることができます。
ドン!っと目の前に現れた爺ヶ岳。北アルプスの爺ちゃん、穏やかな山容でありつつも貫録を感じる。
昨年、初の北アルプスの雪山として登った唐松岳。そこから乗鞍岳へと登り、次に北アルプスで登りやすそうな山として選んだのがこの爺ヶ岳。ここまでは程よい登り応えです。
樹林帯も抜けてきたけど、暴風予報の割にはまだ風は弱め。
山頂も見えたし、残り100分頑張ります。
左手には爺ヶ岳から針ノ木岳へと延びる稜線。そこにポツンと見えるのが雪に半分埋もれた種池山荘。
稜線上に建つこの山小屋は、爺ヶ岳以上に記憶に残っている。泊まってみたい山小屋の1つなんだよね、ここ。屋根のオレンジ色が親近感を感じるぜ!
爺ヶ岳、東側斜面は雪があるけど、西側斜面はほとんど融けてる。
ここから先は雪がなくなるので、アイゼン外す。今回、ピッケルは用無し。アイゼンも登りに関しては使う場所が少なかったです。
ハイマツ帯に入って山頂を目指す。
すっかり雪なし。見える景色に関しては夏山と言ってもいいくらい。
ただ、ここら辺から強風になってきて、風が冷たい。体感温度もやや下がる。
山頂まで残り1時間というところで、お目当てだったあの山が見えてきた。
岩の殿堂、剱岳。雪の剱が見たかったのも爺ヶ岳を選んだ理由の1つ。
カッコいいわ。岩の殿堂、イケメンですわ~!!
後ろを振り返れば、また絶景。北アルプスの山脈を間近に感じられて言うことなし。
見えてからの爺ヶ岳も意外と距離がある。まぁ、まだ10時すぎなので焦ることはない。強風予報が出てるけど、天気の崩れはなさそうだしね。
高い山に登るほど、空が近く感じる。
登山をしてない人に登山を勧めることはあまりしないけど、山に登ると色々と自然に対する価値観も変わってくるし、何より日本の自然の雄大を身に染みて感じられる。だから、山に登らないのは損だと思う。自分としては登山をやってて良かったと思える。
槍ヶ岳をバックに――
これも雄大な自然の中に身を置いているワンシーン。
爺ヶ岳までのビクトリーロード。写真では伝わらないけど、ここら辺はかなりの暴風が吹き荒れてました。
吹き荒れる風に吹き飛ばされそうになりながら山頂を目指す。風速は20mくらいあったかな…。晴れているのと気温が高いのが幸いで、そこまで過酷ではなかったが。
剱岳方面もより一層見えてきた。北アルプス立山連峰、あちらは富山県。
手前の稜線が長野県と富山県の県境。
剱岳をバックに種池山荘のオレンジの屋根が目立っている。遠目に見ると可愛い山小屋。
あの山小屋に泊まったら、剱岳のモルゲンロートなんかも見れるのかな?
もう1つ見るべきは南西方向。
見えてきた立山。先ほどまで主役だった針ノ木岳も右奥の立山がその座を奪っていく。日本を代表する山たちが周りにひしめいていて、本当に贅沢な眺め。
針ノ木岳の奥に見えてきたのは薬師岳かな?
名峰揃いの景色に感動しながら、標高2670mの山頂へ。
11時ちょうど、爺ヶ岳山頂に到着。山頂は相変わらず風が吹き荒れてました。
登りに4時間半を要したけど、危険箇所もなくて割とあっさり登頂。日帰りとしてはちょうど良いレベルでした。
爺ヶ岳南峰頂上。
爺ヶ岳中峰、北峰を経て立ちはだかるのが鹿島槍ヶ岳。
双耳峰の鹿島槍ヶ岳。
鹿島槍は前回登った時は展望が全く望めなかった山なので、別に積雪時じゃなくてもいいからもう1回は登っておきたい。
風は強いけど、気が済むまで北アルプスの山脈を堪能させてもらう。
やっぱり爺ヶ岳からの展望と言えば剱岳か。手前のオレンジの小屋はもはやミニチュアサイズ。周りの山々が大きすぎる。
三角点とケルン。
山頂から記念撮影。「いつか残雪の剱岳も登ってやるから待ってろよ!」と言ってますが、おそらくそんな日は来ない…
山頂にいたのは15分ほど。風が強いので、そそくさと退散。来た道を戻ります。
この写真、何気にお気に入りの1枚。自然体の仲間の姿を撮るのが楽しいわ。
ダイナミックな景観を目の前にしながらの下山。ピストンだけど、帰りは帰りで十分楽しめる。
南尾根途中の展望台。
行きでアイゼンを脱いだところでお昼休憩。
このお昼休憩がなければ、”奴”に出くわしかもしれないと思うと、昼飯食べておいて良かった。
30分の休憩の後に下山再開。
ジャンクションピークから爺ヶ岳とのお別れ。
楽しい山だったので、残雪期に登りたい山が減ってきたらまたお邪魔させてもらいます。
登りできつかった斜面を一気に下る。
脇には行きで自分たちが付けたトレースが残ってたけど、その中にひときわ巨大な足跡が…
熊。しかもこの足跡の大きさからすると、かなりでかいんじゃ…。足跡も新しかったので、ほんの数分前に熊が横切っていったみたい。下山中にすれ違った人に話聞いたら、遠目で熊を見たとのことで、、、。
冬眠から覚めて、腹ペコで食欲旺盛であろう熊。いよいよ熊たちも動き出す時期になったか。
右の樹林帯に熊が逃げ込んだようなので、気持ち左わきを歩いて行く。
熊に遭遇したことはないけど、これだけ登ってればいつか鉢合わせになるんじゃないかって思ってる。
南尾根は麓が見えてる分、高度感が半端ない。目の前には北アルプスの山壁、迫力ありすぎます。
景気づけにいきま~す!\(^o^)/
北アルプスに向かって、大ジャンプをかましてみた。この開脚は何点ですか?
登りで体力削られた雪の斜面も下りならあっという間。ヒップそりでもすれば相当なスピードが出るだろうけど、谷側に落ちかねないので、やめたほうが良さそう。
雪庇の名残。厳冬期の風と雪の強さを垣間見る。
樹林帯に入ってからは来た道をそのまま戻るだけなので省略。
南尾根に限らず、標準ルートでないところは登りよりも下りが迷いやすいので、要注意。
14時20分、麓まで下山。暑すぎたので、扇沢で水浴び。これが気持ちよすぎる。
下山してからの沢での水浴びって、、やってることはもう夏山だな。
14時半、爺ヶ岳駐車場へ戻る。お疲れ様でしたm(__)m
駐車場から見た針ノ木岳の稜線。朝と比べても雪が融けたのがよくわかる。
下山後の温泉は、やっぱりここか。「薬師の湯」。扇沢からの帰り道にある温泉で、バス停もあるので公共交通利用でも来ることができます。
広さ、綺麗さ共に文句なし。
温泉後はそのまま帰っても良かったけど、大町市にある観光地に寄り道。
それがここ、大町山岳博物館。ロゴが可愛い。
山に登る者として、その歴史についてもちゃんと勉強しておかないといけないよな。
…まぁ、17時過ぎてたんで閉まってたけどさ、、、orz
でも、ここは高台にあるので、来て損はない場所です。
こんな感じで北アルプスを一望!麓の大町市からいかに近くに北アルプスが聳えているかがよくわかる。
もともと桜の名所として花見目的で博物館にやってきたんだけど、桜は少し時期が早くてまだ咲いてませんでした。
それでも、この展望にありつけたんだから収穫としては十分。
夕暮れ時の北アルプスと空の色が美しすぎる。大町市の人は毎日この景色を眺められるのかと思うと、羨ましさを感じずにはいられない。
こうして、夕日の北アルプスに見守られながら長野を後にしました。
登った山を下山後に眺めて終わるってのは、一日の旅を振り返れる意味でもいいもんだね。
爺ヶ岳日帰り登山の旅も充実感に満たされて終了。
~~~~~~~~~~~~
北アルプス爺ヶ岳の日帰り登山。時間としては往復8時間程度の短い山行ではあったけど、今回も天気に恵まれて良い景色に出会えました。
南尾根は雪も少なくて道が明瞭だったので割と簡単だったけど、状況次第じゃ当然難易度も変わります。去年の同時期の記録では、長時間のラッセルを強いられた人もいたみたいだし。
コンディションには恵まれすぎた感はあるけど、とりあえず無事に登れて一安心。
3年前には見れなかった景色。針ノ木岳の他にも、お目当ての剱岳や鹿島槍ヶ岳も見れて目的としては十分達成できたしね。
前回の乗鞍岳は北アルプスでありながら少し距離が離れているので俯瞰してみる感じがしたけど、今回は北アルプスのど真ん中にいる感覚を味わえました。
ギリギリ熊との遭遇も回避できたけど、熊さんも動き出す時期になってきましたね。
今年に入ってから例年以上に山に登っている気がするけど、山の本格的なシーズンとしてはこれから。雪が消えていくのが寂しくもあるけど、花や新緑と山の魅力も移り変わっていくので、これからの山がますます楽しみ。
登れるときに登っておこうスタンスで、もうしばらくは山のペースを落とさずに登ろうかと思ってます。山の記録が全然追い付かないけど、書きたい時に一気に書くスタイルなので、次の記事も書きたくなったらアップします。
良ければまた見に来てくださいm(__)m
北アルプス、残雪の爺ヶ岳より―――
おしまい
↓↓ブログランキング参加中↓↓
毎度読んで頂きありがとうございます
【日程】
2015年3月18日
【コースタイム】
爺ヶ岳登山口(6:30) — 八ッ見ベンチ(7:10) — 南尾根取り付き地点(7:15) — ジャンクションピーク(9:20) — 爺ヶ岳南峰(11:00) — 爺ヶ岳登山口(14:30)